
タスクを並べて進めるだけでは、複雑な工程や依存関係を把握しきれず、遅延や工数超過を招く恐れがあります。
こうした課題を防ぐのに役立つのが、PMBOK(Project Management Body of Knowledge)で整理された「プロジェクト管理の10の項目(知識エリア)」です。
このフレームワークを活用すれば、何を・いつ・どのように管理すべきかが明確になり、現場レベルでも安定した進行を実現できます。
本記事では、PMBOKが定義する10の管理項目の基本と、実務での活用ポイントをわかりやすく解説します。属人的な管理を防ぎ、チーム全体で円滑にプロジェクトを進めるためのヒントを見つけてください。
プロジェクト管理の項目とは
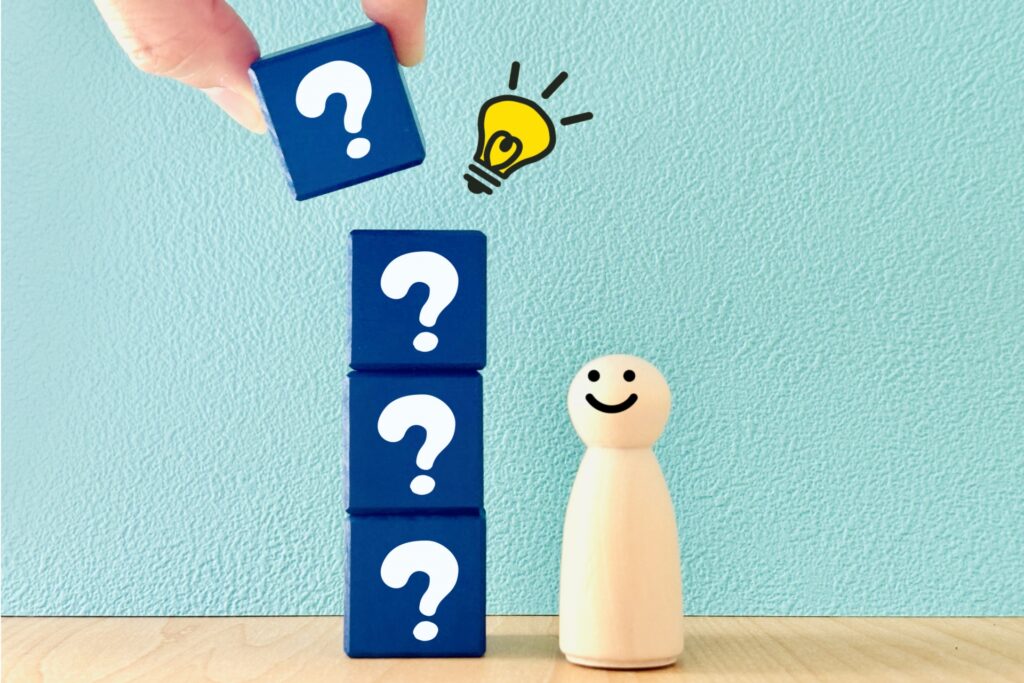
プロジェクト管理における「項目」とは、プロジェクトを成功に導くために監視・コントロールすべき対象を指します。これらを適切に管理することで、プロジェクトの目的達成に向けた道筋が明確になります。
プロジェクト管理項目が重要な理由
プロジェクトの成功基準であるQCD(品質・コスト・納期)を達成するためには、「何を管理するか」という管理項目を明確にし、可視化することが重要です。
プロジェクト進行中には、「品質レビューのタイミングが曖昧」「工数がどこで増えているかわからない」「情報共有が不十分」といった問題が発生する場合があります。これらは個別のトラブルではなく、管理項目が定義されていないことが原因と言えます。
管理項目が明確であれば、QCDに影響する要素を事前にコントロール可能です。
プロジェクト管理項目とPMBOKの関係
プロジェクト管理の各項目を体系的に整理したものが、「PMBOK」です。プロジェクトマネジメント協会(PMI)が策定した国際標準のガイドラインであり、管理対象を「10の知識エリア」として定義しています。
このフレームワークを理解することで、管理の抜け漏れを防ぎ、プロジェクトの成功率をより高められます。PMBOKについての詳しい内容は、以下の記事をご参照ください。
PMBOKに基づく10の管理項目
本章では、PMBOK第6版で定義されている「10の知識エリア」に則して、各管理項目の内容を解説します。
1. 統合管理
統合管理は、プロジェクト全体の整合性を確保し、複数のプロセスや知識エリアを調和させる中心的な管理領域です。個々のタスクが順調に進んでいても、全体目標と整合していなければ成果にはつながりません。
統合管理では、優先順位の判断や変更管理、全体最適のための意思決定を行います。主な活動には、プロジェクト憲章やマネジメント計画書の策定、変更要求の統合的管理、プロジェクトやフェーズの終結が含まれます。
統合管理が機能することで、プロジェクトの方向性が一貫し、チーム全体が共通の目標に向かって進む体制を維持できるのです。
2. スコープ管理
スコープ管理は、プロジェクトで「やること」と「やらないこと」を明確に定義するための管理領域です。特にシステム開発では、後から仕様追加が多発する「スコープクリープ」が発生し、納期遅延やコスト超過の原因となる可能性があります。
そのため、初期段階でスコープを明確に定義し、関係者の合意を得た上で、変更が発生した場合は正式な変更管理プロセスを通じて判断することが重要です。
スコープを適切に管理するポイントは、以下の通りです。
| スコープ管理のポイント | 具体例 |
|---|---|
| 要求事項の収集 | 顧客やユーザーから必要な機能をヒアリングし、要件定義書にまとめる |
| スコープの定義 | 収集した要求をもとに、プロジェクトで実現する成果物と作業範囲を具体化する |
| WBS(作業分解構成図)の作成 | スコープを細かい作業単位(タスク)に分解し、全体像を可視化する |
| スコープの管理 | 変更要求があった場合の影響を評価し、正式な承認手順を経て反映する |
3. スケジュール管理(ガントチャートとの関連)
スケジュール管理は、プロジェクトの納期を守るために、各タスクの開始・終了時期や順序を計画し、調整するための管理領域です。タスク同士の依存関係やリソース配分を整理することで、進捗遅延や工数超過を未然に防げます。
実務ではガントチャートを活用することで、タスクの全体像や進行状況を直感的に把握可能です。遅れや前倒しをガントチャート上で確認できるため、スケジュール調整の判断が迅速になり、結果としてプロジェクト全体の納期遵守率を高めることにつながります。
4. コスト管理(工数管理と連動)
コスト管理は、プロジェクトにかかる費用や工数を把握し、予算内で効率的に進行できるよう調整する管理領域です。特に人件費の割合が大きいプロジェクトでは、工数管理との連動が欠かせません。
実際の作業時間と計画工数を比較することで、どの工程で工数が膨らんでいるのか、どのタスクがコスト圧迫要因となっているのかを早期に把握できます。
差異を発見した時点でリソース配分や優先順位を見直せば、最終的なコスト超過を防ぎ、健全なプロジェクト運営につなげられます。
コスト管理で実施すべき主な項目は、以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コストの見積もり | 各タスクに必要な工数(人時・人日)を算出する |
| 予算の設定 | 見積もりに基づき、プロジェクト全体の予算を策定する |
| コストのコントロール | 計画と実績を比較し、予算超過の兆候を早期に発見・対策する |
5. 品質管理
品質管理は、成果物が顧客の要求仕様や定められた品質基準を確実に満たしているかを確認・保証するための管理領域です。品質が担保されないまま納品してしまうと、信頼の低下を招くだけでなく、手直しや再テストによって余分な工数・コストが発生します。
品質管理では「不具合を見つける」だけでなく、「不具合を生まないプロセスを設計する」ことも重視されます。これにより、再発防止と継続的なプロセス改善の実現が可能です。
以下は、品質管理のプロセスの概要です。
| プロセス | 内容 |
|---|---|
| 品質計画 | 達成すべき品質基準と、その測定方法を定義する |
| 品質保証 | プロジェクトが品質基準を満たすプロセスで進行しているかを監査・評価する |
| 品質管理 | 成果物をテスト・レビューし、欠陥を特定・修正する |
6. 資源管理
資源管理は、プロジェクトに必要な人材・設備・ツールなどのリソースを、適切なタイミングで確保し効率的に活用するための管理領域です。
リソースの不足や偏りは、進捗遅延や品質低下の原因となるため、計画段階から継続的なモニタリングまで一貫した管理が求められます。
資源管理には、以下のような活動があります。
| 活動内容 | 目的・具体例 |
|---|---|
| 必要リソースの洗い出し | 各タスクに必要な人材、ツール、設備を明確にする |
| リソースの確保 | 必要なスキルを持つ人材のアサイン、外部委託の検討 |
| スキルの可視化 | スキルマトリックスでメンバーの能力を一覧化する |
| タスクへの割り当て | スキルや稼働状況を踏まえてタスクを適切に振り分ける |
| リソース状況のモニタリング | 工数の消化状況や負荷の偏りを定期的に確認する |
中でも重要なのが、人的資源(チームメンバー)の管理です。スキルや稼働率を可視化し、過負荷の偏りやミスマッチを防ぐことで、チーム全体の生産性と士気を高めることができます。
7. コミュニケーション管理
コミュニケーション管理は、プロジェクトに関わるすべてのステークホルダーに対して、必要な情報を適切なタイミングと方法で共有するための管理領域です。
情報共有の不足や誤解は、進捗遅延やチーム内の不協和につながるため、計画的な情報伝達が欠かせません。
まずは、以下の観点でコミュニケーション計画を立てます。
| 例 | 内容 |
|---|---|
| 何を | 進捗状況、課題、リスク、変更点など |
| 誰に | 顧客、上司、チームメンバー、関連部署 |
| いつ | 毎日(朝会)、毎週(定例)、毎月(報告会) |
| どのように | 会議、報告書、チャットツール、プロジェクト管理ツール |
計画に沿って情報を共有した後は、相手に正しく伝わっているかや、認識のずれがないかを確認することが重要です。さらに、情報伝達の方法や頻度を定期的に見直し、最適なコミュニケーション体制を維持します。
効果的なコミュニケーションは、チームの士気向上やトラブルの早期発見につながり、プロジェクト全体の推進力を高める基盤となります。
8. リスク管理
リスク管理は、プロジェクトの目標達成を妨げる可能性のある不確実な事象(リスク)を事前に特定・分析し、影響を最小限に抑えるための管理領域です。
問題が発生してから対応するのではなく、予測し、先手を打つことが成功の鍵となります。
以下のようなステップで、リスク管理を実行します。
| リスク管理のステップ | 具体例 |
|---|---|
| リスクの特定 | 「仕様変更の多発」「担当者の急な離職」「新技術の導入失敗」などの要因を洗い出す |
| リスクの分析 | 発生確率と影響度を評価し、優先順位をつける |
| リスク対応計画 | 優先度の高いリスクに対し、「回避」「軽減」「移転」「受容」などの対策を立てる |
| リスクの監視 | 計画が適切に実行されているか、対策が機能しているかを定期的に確認する |
リスク管理を徹底することで、既存リスクだけでなく、新たに発生するリスクにも迅速に対応でき、プロジェクト全体を安定的に進行させることができます。
9. 調達管理
調達管理は、プロジェクトに必要な製品やサービスを外部から購入・契約するための管理領域です。
ハードウェアの購入、ソフトウェアライセンスの契約、外部ベンダーへの開発委託など、社内で賄えないリソースを適切に調達することを目的とします。
主な活動内容は以下の通りです。
- 調達計画の策定
- 発注先の選定
- 契約の締結と管理
- 納品物の検収と支払い
業者選定を費用だけで判断すると、品質低下や納期遅延などのリスクを招く恐れがあります。そのため、技術力・実績・サポート体制などを総合的に評価し、長期的なパートナーシップの観点で選定することが重要です。
10. ステークホルダー管理
ステークホルダー管理は、プロジェクトに関わるすべての人や組織を特定し、意見や要望を調整しながら良好な関係を築くための管理領域です。ステークホルダーには、顧客や上司だけでなく、チームメンバー、関連部署、さらにはエンドユーザーまで含まれます。
まずは、誰がプロジェクトの成功に大きな影響を持つか(キーパーソン)を特定し、それぞれの関心事や影響力を分析してください。その上で、関与度合いに応じたコミュニケーション戦略を立てることで、情報の行き違いや誤解を防ぎ、円滑なプロジェクト推進が実現します。
効果的なステークホルダーマネジメントは、チーム内外の信頼関係を強化し、リスクや課題の早期発見にもつながります。
【一覧表付き】プロジェクトの5フェーズごとに必要な管理項目
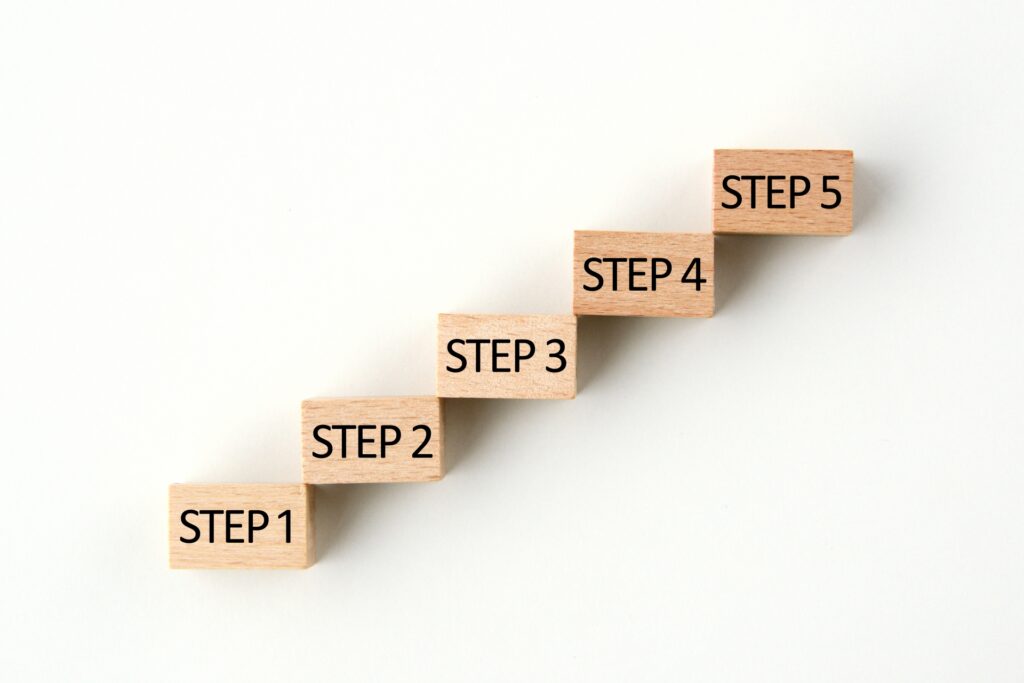
PMBOKでは、プロジェクトを5つのフェーズに分けて管理します。本章では、各フェーズで特に重要な管理項目と、作成すべき主な成果物を一覧でご紹介します。
1. 立ち上げフェーズ
立ち上げフェーズは、プロジェクトの目的・範囲・関係者の認識を統一する準備段階です。方向性が不明確なまま進むと後工程で混乱を招くため、統合管理で方針を整理し、ステークホルダー管理で関係者の認識を揃えます。
主な成果物は以下の通りです。
- プロジェクト憲章(目的・範囲・体制の明文化)
- ステークホルダー一覧(関係者と役割・期待値の整理)
立ち上げを適切に行うことで、プロジェクトの基盤が固まり、計画フェーズをスムーズに進行できます。
2. 計画フェーズ(WBS・タスク設計)
計画フェーズでは、立ち上げで定義した目的や方針を具体的な実行計画に落とし込む段階です。スコープ・スケジュール・コスト・リスクなど主要な管理領域を整理し、実行のための全体像を明確にします。
主な成果物は以下の通りです。
- プロジェクト計画書(全体方針と管理方針の整理)
- WBS(作業の構造化とタスク分解)
- ガントチャート(スケジュールの可視化)
- リスク管理表(課題と対応策の一覧化)
さらに、資源・コミュニケーション計画も併せて策定し、実行に備えた体制を整えます。計画を丁寧に行うことで、実行段階での手戻りを防ぎ、スムーズな進行が可能になります。
3. 実行フェーズ(課題・進捗管理)
実行フェーズは、計画を行動に移し、成果物を完成させる段階です。
統合管理で全体進行を調整し、品質管理で成果物の品質を確認し、コミュニケーション管理で関係者と情報を共有します。同時に、リスク・資源・調達管理を連携させることで、トラブルや遅延を未然に防ぎます。
主な成果物は以下の通りです。
- 進捗報告書(タスク状況や課題の記録)
- 議事録(会議内容や意思決定の共有)
- 課題管理表(課題・担当・対応状況の一覧化)
計画に基づいて確実に実行・調整を重ねることで、プロジェクトの品質とスピードを両立できます。
4. 監視・コントロールフェーズ
監視・コントロールフェーズは、計画と実績の差を把握し、必要に応じて調整を行う段階です。統合管理で変更を適切に承認し、スケジュール・コスト・品質を継続的に確認することで、問題の早期発見と迅速な対処を実現します。
主な成果物は以下の通りです。
- 実績報告書(進捗やコスト消化の記録)
- 変更管理記録(変更内容・承認状況・影響範囲の整理)
継続的なモニタリングにより、計画の精度を高め、プロジェクト全体を安定的に運営できます。
5. 終結フェーズ(成果物レビュー・ふりかえり)
終結フェーズは、成果物を最終確認し、プロジェクトを正式に完了させる段階です。統合管理で全体を評価し、計画どおり成果物が納品されたかを確認します。
また、ふりかえり(KPT)を通じて課題や改善点を整理し、次回以降のプロジェクトに活かします。
主な成果物は以下の通りです。
- プロジェクト完了報告書(成果物と実績のまとめ)
- ふりかえり(KPT)議事録(Keep・Problem・Tryで改善点を整理)
適切な終結は、知見の蓄積と組織のプロジェクト成熟度の向上につながります。
フェーズと管理項目の対応一覧表
各フェーズの主な目的・重要な管理項目・成果物をまとめた一覧です。チェックリストとして活用することで、管理漏れを防ぎ、スムーズな進行を支援します。
| フェーズ | 主な目的 | 特に重要な管理項目 | 主な成果物 |
|---|---|---|---|
| 1. 立ち上げ | プロジェクトの目的を定義し、公式に承認を得る | 統合管理/ステークホルダー管理 | プロジェクト憲章/ステークホルダー一覧 |
| 2. 計画 | 目的達成のための具体的な方法、スケジュール、予算を策定する | スコープ管理/スケジュール管理/コスト管理 | プロジェクト計画書/WBS/ガントチャート/リスク管理表 |
| 3. 実行 | 計画書に基づき、タスクを実行して成果物を作成する | 統合管理/品質管理/コミュニケーション管理 | 進捗報告書/議事録/課題管理表 |
| 4. 監視・コントロール | 進捗を測定し、計画との差異を分析して是正措置を講じる | 統合管理/スケジュール管理/コスト管理/品質管理 | 実績報告書/変更管理記録 |
| 5. 終結 | 成果物を正式に納品し、プロジェクトを公式に完了させる | 統合管理/調達管理 | プロジェクト完了報告書/ふりかえり(KPT)議事録 |
プロジェクト管理のフェーズについては、以下の記事で詳しく解説しています。
プロジェクト管理項目を実務で活かす5つのポイント

知識として管理項目を理解するだけでなく、実務で使いこなすことが重要です。本章では、プロジェクト管理を円滑に進めるための5つのポイントをご紹介します。
チーム全体で管理項目を共有する
プロジェクト管理はマネージャーだけが行うものではありません。何を、なぜ管理しているのかをチーム全体で共有することで、メンバーの当事者意識が高まります。
プロジェクトの目標や計画、現状の課題を明確に伝えることが、一体感のある強いチームを作ります。
WBSでタスクを分解し可視化する
管理項目を実務で機能させるには、WBSで作業をタスク単位まで分解することが重要です。スコープ管理やスケジュール管理も、実際のタスクが見えていなければ機能しません。
WBSによって「何を・どこまでやるのか」を明確にすれば、担当者や工数の見通しが立ち、ガントチャートなどへの展開もスムーズになります。
WBSの作り方については、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご参照ください。
ガントチャートでスケジュールを直感的に管理する
WBSで分解したタスクを時間軸に落とし込むことで、スケジュール管理を実務レベルで機能させられます。
ガントチャートは、開始日・終了日・担当者・進捗状況を一目で把握できるため、統合管理の判断材料としても有効な技法の一つです。また、タスク間の依存関係を明確にできるため、「どの工程が遅れると全体に影響するか」を直感的に確認でき、早期対策につながります。
定期的な見直しと柔軟な調整
どれだけ綿密に計画を立てても、プロジェクトに予期せぬ変更が発生する場合があります。週次ミーティングなどで定期的に進捗を確認し、状況に応じた調整が重要です。
計画と実績の差異を早期に発見し、迅速に対応する柔軟性がプロジェクトマネージャーに求められます。
プロジェクト管理ツールを導入する
プロジェクト管理ツールの活用で、タスクの進捗状況やスケジュール、課題・リスクの情報を一元管理できます。
ガントチャートやWBSを直感的に確認できるため、計画と実績のギャップもすぐに把握可能です。また、チーム内で情報を共有しやすくなることで、コミュニケーションの円滑化や報告作業の効率化も実現できます。
適切なツールの導入は、プロジェクトの透明性と生産性を大きく向上させます。
よくある質問(FAQ)

本章では、プロジェクト管理に関するよくある疑問を整理し、解説します。
プロジェクト管理項目は何個くらい必要ですか?
PMBOKでは10の知識エリアが定義されていますが、プロジェクトの規模や特性により重点は異なります。小規模プロジェクトでは、スコープ・スケジュール・コスト・品質の4項目を意識するだけでも効果的です。
まずは主要項目から始め、必要に応じて他の領域を取り入れるのが現実的です。
小規模プロジェクトでもPMBOKの項目は必要ですか?
はい、PMBOKの考え方は規模を問わず有効です。
ただし、小規模では詳細な手順よりも、スコープの明確化・リスク予測・進捗確認など、重要項目を簡略化して運用するのが現実的です。
タスク管理とリスク管理の違いは?
タスク管理は「やるべき作業」を整理・進行する活動で、目的は計画通りに作業を完了させることです。
一方、リスク管理は「起こるかもしれない不確実な事象」に備える活動で、目的は問題を予防し影響を最小化することです。
Excelとツールで項目管理する違いは?
Excelは手軽に始められますが、同時編集や最新情報の共有が難しい点が課題です。
一方、プロジェクト管理ツールはガントチャートやカンバンなどを統合し、チーム全員がリアルタイムで状況を共有可能です。通知・レポート機能により、管理の効率が大幅に向上します。
Lychee Redmineでプロジェクト管理項目を効率化

ここまで解説してきた多くの管理項目を、手作業やExcelだけで管理することは非常に手間がかかります。
そこでおすすめしたいのが、7,000社以上の導入実績を誇るプロジェクト管理ツール「Lychee Redmine」です。
ガントチャートとWBSで計画項目を整理
Lychee RedmineはWBSで作成したタスク構造がガントチャートに自動反映されるため、計画変更が発生した場合もリアルタイムで全体スケジュールに反映されます。計画立案から進捗管理までを一気通貫で行え、計画と実行の乖離を防げます。
直感的なドラッグ&ドロップ操作で、タスクの依存関係も簡単に設定が可能です。
工数管理でコスト・リソースを最適化
Lychee Redmineはチケットごとに予定工数と実績工数を記録し、自動で集計します。リソースの過剰・不足をリアルタイムに把握できるため、属人的な工数管理から脱却し、最適な稼働計画を実現できます。
計画と実績の差をグラフで可視化し、コスト超過の兆候を早期に発見可能です。
課題管理でリスクと進捗を同時に把握
Lychee Redmineは課題管理・Wiki・ファイル共有・コメント機能を統合し、情報を一元化します。報告・承認・共有がLychee Redmine上で完結するため、情報の分断や伝達ミスを防げます。
各チケットはガントチャート上のタスクと紐づけられるため、進捗と課題をまとめて把握可能です。
複数プロジェクトを横断的に可視化
Lychee Redmineは複数プロジェクトのタスク・リソース・進捗を統合的に表示可能です。組織全体でリソース配分を最適化し、特定メンバーへの負荷集中や属人化を未然に防げます。
プロジェクトが並行して進行している場合でも、全体像を把握しやすく、迅速な意思決定を実現します。
●Lychee Redmineの料金プラン一覧
Lychee Redmineは、チームの規模や管理レベルに合わせて選べる4つのプランを提供しています。基本機能から高度な分析・管理まで段階的に利用でき、ビジネスプランは無料トライアルも利用可能です。
プラン 月額料金 利用機能 フリー 無料 スタンダード 900円 プレミアム 1,400円 ビジネス[無料トライアルはこちらをお試しできます] 2,100円
プロジェクト管理項目を整理し、計画からリスクまでプロセスを最適化しよう

プロジェクト管理では、各フェーズで必要な管理項目を明確にし、優先順位を意識した運用が欠かせません。統合管理・スコープ管理・リスク管理などを適切に実施することで、課題の早期発見やリソース配分の最適化が可能になります。
ただし、管理項目が多すぎると全体像を見失いやすくなるのも事実です。
この課題を解決するには、多機能プロジェクト管理ツール「Lychee Redmine」の活用が効果的です。WBSやガントチャート、課題管理を一元化でき、計画からリスクまでのプロセスをスムーズに可視化・最適化できます。
現在、30日間の無料トライアルを実施中です。ぜひ実際のプロジェクトで、効率的な管理体制を体感してください。
30日無料トライアルをはじめる
- 多機能ガントチャート/カンバン/バックログ/リソース管理/CCPM/レポートなど
- ・ クレジットカード登録不要
- ・ 期間終了後も自動課金なし
- ・ 法人の方のみを対象
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。





