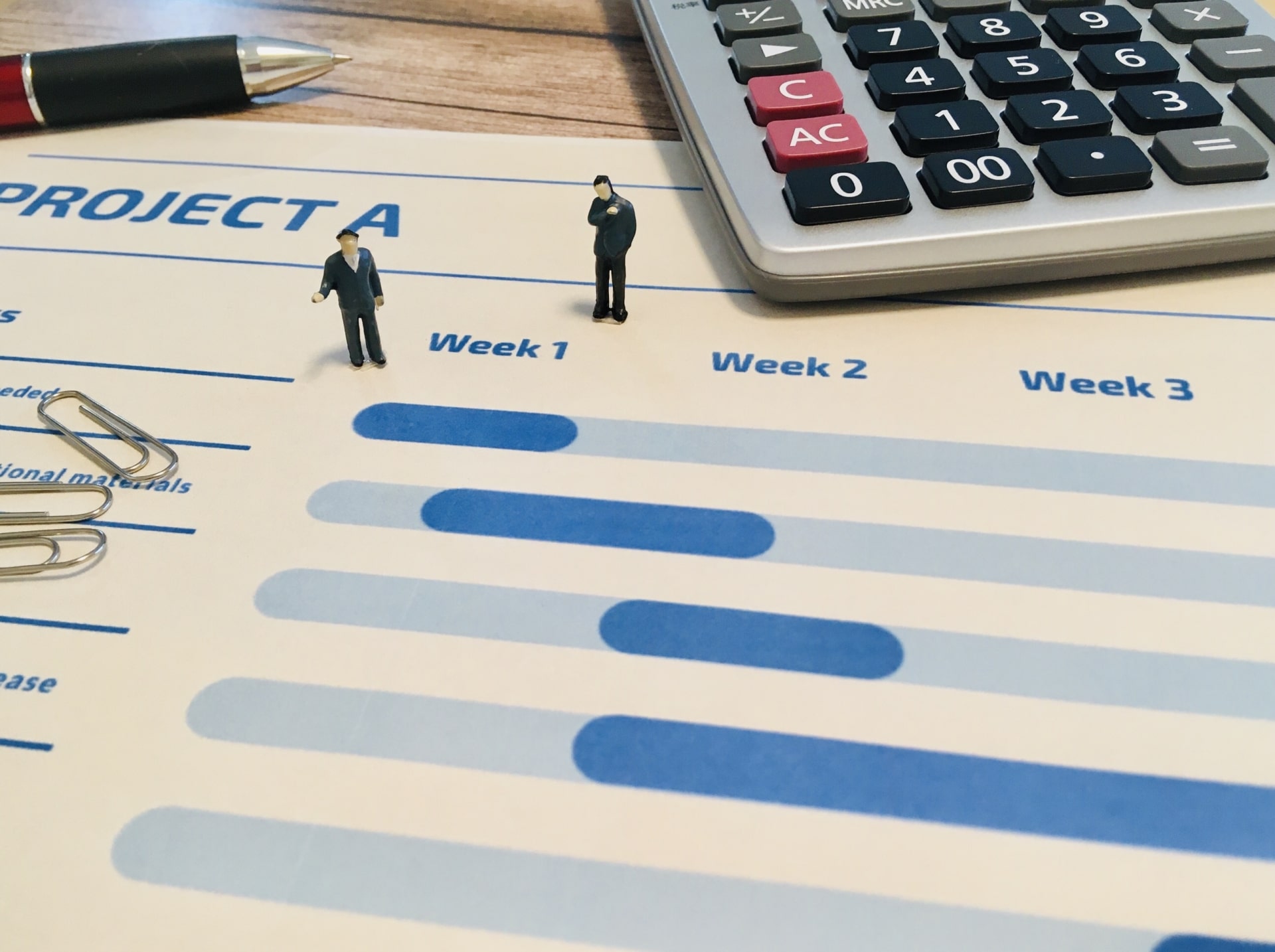「なぜ、うちのプロジェクトはいつも計画通りに進まないのだろう」
「優秀なメンバーが揃っているのに、納期遅延や手戻りが繰り返されてしまう」
プロジェクトマネージャーやチームリーダーであれば、一度はこうした悩みに直面したことがあるのではないでしょうか。多くのプロジェクトが予定通りに進まない原因は、タスクの遅延やリソースの偏り、そして各担当者が設けた過剰なバッファ(安全余裕)にあります。
こうした問題を根本から見直し、納期の確実な達成と効率的な進行を両立させる手法が「CCPM」です。
本記事では、CCPMの基本的な考え方から、バッファ管理の仕組み、リソース配分の最適化、そして実務への応用までをわかりやすく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、自社プロジェクトの進行改善に役立ててください。
CCPM(クリティカルチェーン・プロジェクト・マネジメント)とは

CCPM(Critical Chain Project Management)とは、プロジェクト全体の進行を迅速化することを目的とする管理手法です。
個々のタスクを最短で終わらせることよりも、プロジェクト全体の完了を最優先に考える点が特徴です。
CCPMの概要と目的
CCPMとは、制約理論(TOC:Theory of Constraints)の提唱者であるエリヤフ・ゴールドラット博士によって開発されたプロジェクト管理手法です。
従来のように「スケジュール通りに進めること」を目的とするのではなく、プロジェクト全体で最も制約となるリソース(人材・設備など)を中心に計画を立てる点が特徴です。
CCPMでは、タスクの所要時間そのものよりも、「誰が」「いつ」「どのリソースを使うか」といった実際の動きを重視します。これにより、リソースの重複や待ち時間といったボトルネックを未然に防ぎ、無駄のないスケジュール運用が可能になります。
結果として、限られたリソースの中でもプロジェクト全体の最適化を図り、納期を安定して守ることができる手法です。
従来のプロジェクト管理(クリティカルパス)との違い|背景と思想
従来のクリティカルパス法(CPM)は、タスクの順序や所要時間から「最短経路(クリティカルパス)」を算出し、「計画通りに進めること」を重視する手法でした。
しかし実際の現場では、人材や設備の重複、突発的な対応、優先度の変動などにより、計画通りに進行しないケースが多発します。その結果、特定の遅延が全体に波及し、スケジュールが崩れることも珍しくありません。
そこで登場したのが、CCPMです。CCPMは、従来の「各タスクに余裕を持たせる」発想から脱却し、プロジェクト全体でバッファを一元管理する仕組みへと転換しました。
スケジュール管理だけでなく、リソース配分・進捗報告・優先順位付けまでを包括的に運用することで、計画と実行の乖離を最小限に抑え、より現実的なプロジェクト運営を実現できます。
タスク管理・リソース配分の最適化を重視する背景
近年のプロジェクト現場では、複数の案件を同時に進める「マルチタスク化」や、限られた人員による「並行作業」が当たり前になっています。
結果として、一部のリソースに負荷が集中し、全体の進行が遅れるといった問題が頻発していました。CCPMは、こうしたリソース競合やタスク間の依存関係を整理し、最も制約となるリソースを基準にスケジュールを構築します。
さらに、タスク単位ではなくプロジェクト全体としてバッファを設けることで、スケジュールに遅れがあっても、影響を吸収し安定した進行を可能にします。
CCPMが生まれた背景と導入が進む理由

プロジェクトが複雑化しリソース不足が進む中、従来のスケジュール管理では限界が見え始め、より実践的で柔軟な手法としてCCPMの導入が広がる傾向にあります。
特に、納期遵守や品質確保が重視される現場では「計画を守る」から「制約を管理する」へと発想を転換する必要があり、そうした解決策としてCCPMが注目されています。
従来のスケジュール管理が抱える課題
従来のガントチャートを中心としたスケジュール管理では、各タスクごとに「バッファ(余裕時間)」を設けるのが一般的でした。しかし、このように個々のタスクにバッファを分散して設定すると、重複や無駄が生じやすく、結果として全体の進行が非効率になります。
さらに、担当者が「まだ締切まで時間がある」と考えて着手を遅らせる「学生症候群」や、与えられた時間いっぱいまで作業を続けてしまう「パーキンソンの法則」などの心理的要因も、プロジェクトの遅延を引き起こす原因となります。
このように、個別最適に依存した管理手法では、全体の納期を安定して守ることが難しいのです。
スケジュール設計を強化したい方は、下記の記事でガントチャートの基本とWBSとの使い分けをチェックしてください。
マルチプロジェクト・リソース制約時代に対応するための発展
近年では、複数のプロジェクト(マルチプロジェクト)を同時に進行し、限られた人材や設備を共有する体制が一般化しています。その一方、特定のリソースに業務が集中することで、他の作業に影響が出る「リソース制約」が頻繁に発生しているのが現状です。
こうした環境下では、CCPMが有効とされています。リソースの可用性を考慮したスケジュール設計に加え、全体的な進行に応じてバッファを一元管理することで、同時進行による負荷を軽減できるためです。
結果として、複数の案件を並行して進めながらも、納期の安定化につなげられます。
PMBOKにも関連する「プロセス思考」の流れ
CCPMの根底にあるのは、プロジェクトを単なるタスクの集合ではなく、「価値提供の連続したプロセス」として捉える思考です。
上記の概念は、プロジェクトマネジメント知識体系ガイド「PMBOK第7版」において重視される、成果創出を目指す「パフォーマンスドメイン」の考え方と高い親和性があります。
CCPMは、タスクを並べるだけのスケジューリング手法ではありません。プロジェクトをより効率的かつ効果的に完了させるためのシステム改善を促す哲学として導入が進められています。
具体的には、プロジェクト全体の中で最も進行を妨げる要因(クリティカルチェーン)に注目し、その制約を解消することで全体の流れをスムーズにする考え方です。こうしたボトルネックの改善を繰り返すことで、プロジェクト全体の生産性と成果(アウトプット)を高められます。
CCPMの核となるクリティカルチェーンとバッファ管理

CCPMの成功は、スケジュール管理上のクリティカルチェーンの把握と、遅延リスクを効率的に吸収する集中バッファ管理といった考え方に基づいています。
クリティカルチェーンとクリティカルパスの技術的な違い
クリティカルパス(CP)とクリティカルチェーン(CC)は、どちらも「プロジェクトの完了に直接影響する最長経路」を示しますが、考慮する要素に決定的な違いがあります。
| 比較項目 | クリティカルパス(CP) | クリティカルチェーン(CC) |
|---|---|---|
| 計算基準 | タスクの順序と所要時間 | タスク順序に加えてリソースの可用性を考慮 |
| 管理対象 | スケジュール(時間軸) | リソースとスケジュールの両方 |
| リスク対策 | 各タスクに安全余裕を設定 | プロジェクト全体でバッファを一元管理 |
| 想定環境 | 理想的な条件で進行 | 実際の制約を前提に運用 |
表の内容を踏まえると、CCPMは現場の制約を考慮し、全体最適を実現する実践的なプロジェクト管理手法であることがわかります。
従来のクリティカルパス法(CP)では、人員や設備といったリソースの競合による待ち時間が考慮されず、計画と実態の間に乖離が生じやすいという課題がありました。
一方、CCPMはリソース制約を含めた現実的な経路(クリティカルチェーン)を重視し、これをプロジェクト全体のボトルネックとして管理します。
そのため、担当者やリソースの可用性まで考慮して計画を立てている場合、それはすでにクリティカルチェーンによるマネジメントを実践していると言えるでしょう。
タスクの余裕時間を集約して管理するバッファの仕組み
CCPMの特徴は、タスクごとに設定された余裕時間をそのまま使用せず、プロジェクト全体で集約して管理することです。
こうした余裕時間を「バッファ」と呼び、クリティカルチェーンの終点や重要なマイルストーンに集中させることで、各作業における不必要な待機や過大な余裕時間を防ぎます。
バッファ管理を行うことで、個別のタスクや作業で発生した遅れを吸収し、プロジェクト全体の納期に影響を及ぼさず全体最適なスケジュール運営を実現できます。
さらに、バッファ状態のモニタリングにより、プロジェクト進行の問題点を早期に発見できるため、柔軟な調整が可能です。
リソース配分の最適化と遅延防止の考え方
CCPMでは、まずリソース(人や設備など)の制約やボトルネックを把握し、必要に応じて同時進行を制限することが重要です。なぜなら、特定の担当者や設備に作業が集中すると、他のタスクが待機状態になり、全体の進行が遅れてしまうからです。
そのため、最も負荷の高いリソースを優先的に調整し、タスクの順番や担当を最適化します。さらに、リソース配分の見直しに加えてバッファ管理を組み合わせることで、複数のタスクを同時に進めても、無理なく期限内に完了できる体制を築けます。
リソース配分でお悩みの方は、下記の記事でリソースの基礎と効果的な活用法を確認してみましょう。
プロジェクトの安全弁となる3種類のバッファ

CCPMでは、プロジェクトの不確実性に備えるため、計画段階で3種類のバッファを設定します。これらのバッファは、遅延リスクを吸収し、安定した進行を支える重要な安全弁として機能します。
プロジェクトバッファ
プロジェクトバッファは、プロジェクト全体の納期を守るために中央で一元的に管理される余裕時間です。スケジュール上はクリティカルチェーンの末尾に配置され、個々のタスクで発生した遅れや予期せぬトラブルを吸収し、全体スケジュールへの影響を最小限に抑えます。
タスクごとに余裕時間を分散させず、全体でバッファを集中管理することで、限られた時間を効率的に使い、プロジェクトの安定した進行を実現できます。
そうすることで、予期せぬ遅れが発生しても影響を最小限に抑える安全弁として機能し、プロジェクト進行状況の把握や調整にも役立つのです。
合流バッファ
合流バッファは、複数の並列タスクが一つのポイントで合流する際に、遅延を吸収するために設置されます。並列タスクは進捗のバラつきが発生しやすく、タスクが合流する際に、後続の作業が遅れる恐れがあるからです。
合流バッファを設けることで、各タスクの遅れをまとめて吸収し、プロジェクト全体の進行に影響を与えずに次工程へスムーズに引き渡せます。
結果として、タスク遅延の連鎖を防ぎ、スケジュール全体の安定性と信頼性を高めることができます。
リソースバッファ
リソースバッファは、担当者の切り替えや設備準備による待機時間など、リソース依存で発生する遅延を防ぐために設けられる余裕時間です。特定の担当者や設備が次のタスクに着手できるよう、あらかじめ余裕を持たせることで、ボトルネックや待機時間の発生を抑えます。
これにより、リソースの稼働率が高まり、複数タスクを並行して進める場合でもスムーズな進行を維持できます。リソースバッファを適切に活用することで、プロジェクト全体の効率を高め、納期遵守につなげることができるのです。
CCPM導入のメリットとプロジェクト管理への効果

CCPMの導入によって、単に納期を守りやすくなるだけでなく、プロジェクト全体の管理品質が向上します。
本章では、CCPMがもたらす具体的な効果を3つの側面に分けて解説します。
進捗の見える化で遅延リスクを早期発見できる
CCPMでは、バッファバーやフィーバーチャートといった可視化ツールを活用し、プロジェクト進捗をリアルタイムで把握できます。バッファバーにより、各タスクやプロジェクトバッファの消費状況が一目でわかるため、遅延の兆候を早期に発見可能です。
また、フィーバーチャートを用いることで、プロジェクト全体の健康状態やリスクの集中個所を視覚的に把握でき、問題が顕在化する前に対策できます。
チーム連携が強化され、優先度に基づく効率的な進行が可能に
CCPMでは、タスクの優先度が明確化されるため、チーム内における情報共有やボトルネックの認識が容易になります。担当者間で優先順位を共有することで、限られたリソースを効率的に配分でき、重要なタスクへ集中して取り組めます。
また、クリティカルチェーンにおけるボトルネックやリソースの衝突点が可視化されるため、チーム全体で協力しながら遅延を防ぐ行動が取りやすくなるのです。結果として、効率的な進行とチーム連携の強化が同時に実現します。
タスクとリソースの最適配分でプロジェクト全体の安定化を実現
CCPMは、マルチプロジェクト環境下にあるタスクとリソースの最適配分を可能にします。リソースのボトルネックや待機時間を事前に把握し、必要に応じて同時進行を制限することで、全体の進行を安定化させます。
さらに、プロジェクトバッファやリソースバッファを活用すれば、予期せぬ遅延やリソース変動にも柔軟に対応可能です。このように、CCPMは複数のプロジェクトを並行して進行させる状況でも、納期遵守と進行の安定化を両立できる手法です。
CCPM導入前に確認したい2つの注意点

CCPMは効果的な手法ですが、導入すれば必ず成功するわけではありません。
導入を検討する際には、以下2つの点について、自社の状況と照らし合わせて確認することが重要です。
部署間・チーム間での協力体制が不可欠
CCPMを効果的に導入するには、部署間やチーム間での協力体制が欠かせません。特にリソース共有型の組織では、各プロジェクトやタスクで使用する人材・設備の調整が前提です。
クリティカルチェーンの進行を妨げる要因を正確に特定し、優先度に応じてスケジュール全体を最適化するためには、関係部署間での密なコミュニケーションと合意形成が欠かせません。
協力体制が不十分な場合、CCPMの利点を十分に活かせず、遅延やリソース衝突が発生しやすくなります。
短期・小規模プロジェクトでは導入効果が限定的になりやすい
CCPMは、複数タスクや長期プロジェクトで大きな効果を発揮する手法です。そのため、短期・小規模プロジェクトの場合は、導入にかかる手間やコストの割に、得られるメリットが限定的になりやすい点に注意が必要です。
短期間で完了するタスクやリソース競合がほとんどない環境では、クリティカルチェーンの管理やバッファ設定の効果が十分に発揮されないケースが多くなります。
導入前には、プロジェクト規模や複雑性を評価し、CCPMの適用が合理的かどうかを判断することが大切です。
CCPM導入を成功させる3つのステップ

CCPMの導入は、主に3つのステップで進めるプロセスです。それぞれの段階には、従来のスケジュール管理とは異なる重要な視点と実践ポイントがあります。
本章では、その3つのステップを順を追って解説し、導入を成功させるための具体的な進め方をご紹介します。
ステップ1:リソース制約とクリティカルチェーンの特定
最初のステップは、プロジェクト全体のリソース制約を把握し、クリティカルチェーンを特定することです。ボトルネックとなる人材や設備、特に複数プロジェクトで共有されるリソースを明確にしましょう。
そうすることで、重要タスクの優先度やスケジュール調整の基準が定まり、遅延リスクが発生しやすい部分に対策ができます。クリティカルチェーンを明確にすることにより、全体最適の観点からリソース配分や進行管理を行いやすくなります。
ステップ2:タスク見積もり短縮とバッファ配置による柔軟設計
次は、各タスクの見積もり時間を短縮し、全体としての柔軟性を確保しましょう。従来は担当者が余裕を見込んで長めに設定しがちですが、CCPMでは安全余裕を排し、実際の平均所要時間に基づいてスケジュールを短縮することが特徴です。
代替策として、プロジェクト全体の終盤に「プロジェクトバッファ」、分岐点には「合流バッファ」を配置して予期せぬ遅延を吸収します。
結果として、各タスクが効率的に進行しつつも、全体としては安全性が担保された形でバランスの取れた計画が実現します。
ステップ3:進捗監視とリソースバッファによる実行マネジメント
最後のステップは、進捗状況をリアルタイムで監視し、リソースバッファを用いて進行管理を行います。フィーバーチャートやバッファバーを用いて各タスクやリソースの消費状況を可視化し、遅延やボトルネックを早期に発見しましょう。
リソースバッファを使い、担当者の交代や設備の空き時間を調整することで、全体進行を安定させて遅延リスクを低減できます。継続的な監視と調整により、計画通りの成果物納品ができるようになります。
進捗管理の精度を高めたい方は、以下の記事から最新のプロジェクト管理手法をチェックしてください。
Lychee RedmineでCCPMを効率的に運用|ガント・WBS・工数で「遅れゼロ」を実現

CCPMの考え方を実践し、「遅れゼロ」のプロジェクトを実現するためには、適切なツールが不可欠です。
「Lychee Redmine」は、CCPMの実践を多角的に支援し、プロジェクト管理を次のレベルへと引き上げてくれます。
ガントチャートとWBSでプロジェクト全体を可視化
Lychee RedmineのガントチャートとWBS機能を活用すれば、CCPMの流れを簡単に確認できます。各タスクの依存関係やリソース配置を一目で確認できるため、クリティカルチェーンの進行状況をリアルタイムで追跡可能です。
さらに、WBSでタスクを階層的に整理することで、複雑なプロジェクトでも全体像を把握しやすくなり、関係者間の共通認識を強化します。
結果として、スケジュールのズレやリソースの重複を未然に防ぎ、効率的な進行管理を実現します。
工数管理でリソース・タスク・バッファの整合を最適化
Lychee Redmineの魅力は、工数を管理する機能によってCCPMのリソース負荷計画を再現できる点です。各メンバーの作業時間やタスク進捗を可視化できるため、リソースの偏りや過剰稼働を防ぎ、バランスの取れた進行が可能です。
また、タスクごとの工数データを蓄積・分析することで、今後のスケジュールの精度向上やバッファ設計も改善できます。加えて、クリティカルチェーンに沿ったリソース配分を効率的に調整すれば、全体最適を意識したプロジェクト運営が実現しやすくなります。
課題管理で遅延リスクを早期発見・共有
Lychee Redmineの課題管理機能を活用すれば、CCPMで重要となるバッファ消費率を課題として可視化し、チーム全体でリスクを共有できます。
進捗の遅れやボトルネックをリアルタイムで把握できるため、対応や対策を早期に検討できる点が大きな強みです。また、課題ごとの優先度や影響範囲を明確にすることで、チーム内での迅速な意思決定を促進できます。
これにより、遅延を未然に防ぎ、プロジェクト全体の安定した進行を実現できます。
複数プロジェクトを横断的に管理し、全体リソースを最適活用
Lychee Redmineは、複数のプロジェクトを横断的に管理できるため、マルチプロジェクト環境でのCCPM運用にも最適です。
各プロジェクトの進捗やリソース負荷をまとめて確認できるので、優先度の高いタスクにリソースを集中させる判断が容易になります。さらに、EVM(Earned Value Management)機能を活用すれば、コスト・進捗・成果の定量的な評価も可能です。
こうしたCCPMとの高い親和性によって、組織全体での効率的なリソース活用と納期遵守を両立できます。
CCPM導入で、正確さとチーム連携を両立させよう

CCPMを導入することで、管理の精度を維持しながら、チーム全体の協働体制を強化できます。リソースを最適に配分できるため、納期を守りつつ成果を最大化するプロジェクト運営が可能です。
Lychee RedmineのガントチャートやWBS、工数・課題管理機能を活用すれば、プロジェクト全体の可視化とタスク管理の自動化を同時に実現できます。
さらに、複数プロジェクトを横断的に管理することで、全体リソースを効率的に活用し、CCPMの効果を最大限に引き出せます。
まずは無料トライアルを活用し、安定したプロジェクト運営を体験してみてください。CCPMは、遅延リスクを大幅に軽減し、プロジェクトを成功へ導くための強力なパートナーです。
30日無料トライアルをはじめる
- 多機能ガントチャート/カンバン/バックログ/リソース管理/CCPM/レポートなど
- ・ クレジットカード登録不要
- ・ 期間終了後も自動課金なし
- ・ 法人の方のみを対象
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。