
アジャイル開発に興味を持ち始めた方や、最近プロジェクトに新たに参加された方から、次のような声をよく耳にします。「アジャイル開発では設計書を作らないと聞きました。本当にそんな方法で、きちんとしたシステムが作れるのでしょうか?」
特に、ウォーターフォール型の開発で詳細な設計書の作成に慣れてきた方ほど、この点に強い不安を感じるのも無理はありません。設計書がなければ、仕様の認識にズレが生じたり、品質が低下したり、将来的な保守が難しくなるのではないかと心配される方も多いでしょう。
しかし、結論から言うと「アジャイル開発では設計書を一切作らない」というのは、実は大きな誤解です。
本記事では、その誤解がなぜ生まれたのかという背景から、アジャイル開発における情報共有の本質、そして品質とスピードを両立するための具体策までを徹底解説します。
本記事を読むことで、次のような成果が得られます。
- アジャイル開発における「ドキュメントの本当の役割」を正しく理解できる
- 品質を守りながらスピードも高める具体的な進め方が身につく
- 自分たちのチームに合ったドキュメント活用法を見つけ、安心してプロジェクトを推進できる
設計書に対する漠然とした不安を解消し、アジャイル開発の真の力を引き出すための第一歩を踏み出してください。
そもそもアジャイル開発とは?

アジャイル開発とは、変化の激しいビジネス環境に柔軟に対応するために生まれた開発手法です。従来のように最初から緻密な計画や設計を固定するのではなく、短いサイクルで計画・実装・改善を繰り返すことで、状況に応じた迅速な対応を可能にします。
ここでしばしば誤解されるのが「アジャイルは設計書を作らない」という考え方です。実際には、設計や資料を排除するのではなく、計画を柔軟に更新しながら価値ある開発を進めることこそが本質です。
この言葉が独り歩きした背景には、アジャイルが何を最も重視しているのかという根本的な思想があります。まずは、その思想の原点を理解することから始めましょう。
アジャイル開発では「動くソフトウェア」を最優先する
アジャイル開発の根底には、「アジャイルソフトウェア開発宣言」と呼ばれる基本思想があります。その中で象徴的な一文が、次の価値観です。「包括的なドキュメントよりも、動くソフトウェアを」(参考元:アジャイルソフトウェア開発宣言)
この言葉は、時間をかけて分厚い設計書を作ることが目的化し、結果として顧客にとって価値を生まない状況を避けるために示されています。ドキュメントはあくまで顧客に価値を届けるための手段であり、それ自体が目的ではありません。
アジャイル開発では、まず動くソフトウェアを早期に提供し、顧客からのフィードバックを得ながら改善を重ねていくことに最大の価値がある、という思想が軸に据えられているのです。
「設計書なし」ではなく「計画を柔軟に変える」
アジャイル開発は、決して無計画に進める手法ではありません。ウォーターフォール開発のように、開発開始前にすべての仕様を固定し、詳細な設計書を作り込むスタイルを取らないだけです。
顧客のニーズや市場環境は常に変化するため、最初の計画が最後まで最適であるとは限りません。そこでアジャイル開発では、「必要な情報を、必要なタイミングで、必要な分だけ」 ドキュメント化し、変化に柔軟に対応できる状態を保ちます。
つまり「一切作らない」のではなく、「作りすぎない」「活用しやすく工夫する」 のが実情に近いのです。
アジャイル開発に「設計書は不要」というのは誤解

「動くソフトウェアを優先する」という考え方が、しばしば「設計書は不要」という極端な解釈につながることがあります。しかし、それは大きな誤解です。
アジャイル開発においても、チームの共通認識を形成し、プロジェクトを円滑に進めるためには、設計活動とその成果物としてのドキュメントが欠かせません。
ただし、重要なのはドキュメントの捉え方がウォーターフォール開発とは大きく異なるという点です。以下の表で、その考え方の違いを整理してみましょう。
| 観点 | ウォーターフォール開発 | アジャイル開発 |
|---|---|---|
| ドキュメントの目的 | 開発の全貌を事前に定義し、計画の遵守を促す | コミュニケーションを促進し、共通認識を形成する |
| 作成タイミング | 開発開始前にすべて作成 | 必要になった都度(ジャストインタイム) |
| 詳細度 | 包括的で詳細 | 必要最小限で簡潔 |
| 主な役割 | 指示書、契約の根拠 | 議論のたたき台、備忘録、知識の共有 |
上記のように、アジャイル開発におけるドキュメントはチームを縛るためのものではなく、チームの活動を助けるためのツールとして位置づけられています。
プロダクトバックログとユーザーストーリーが設計の起点
アジャイル開発、特にスクラムというフレームワークでは、プロダクトバックログが設計の出発点です。プロダクトバックログは、プロダクトに必要な機能や修正項目を優先度順に並べたリストです。
プロダクトバックログの各項目は、「ユーザーストーリー」という形式で記述することが推奨されています。ユーザーストーリーは、単なる機能要求ではなく、「誰が・何をしたいのか・それはなぜか」を明確にするためのものです。
| 役割(As a…) | 目的(I want…) | 理由(so that…) |
|---|---|---|
| ECサイトの利用者 | 商品をキーワードで検索したい | 欲しい商品をすぐに見つけられるようにするため |
| サイト管理者 | 人気商品のランキングを確認したい | 在庫管理や販売戦略に役立てるため |
上記のように、ユーザーストーリーは、これから作る機能の「WHY(なぜ作るのか)」をチーム全員で共有するための、最初の設計情報となります。
受け入れ基準を明確にすることで品質と認識を統一できる
ユーザーストーリーにおいて「いつ完成したと見なせるか」を定義するのが「受け入れ基準(Acceptance Criteria)」です。これを明確にすることで、開発者とプロダクトオーナーの間で「完成」の認識がずれるのを防ぎ、品質を担保できます。
例えば「ECサイトの利用者として、商品をキーワードで検索したい」というユーザーストーリーに対しては、以下のような受け入れ基準が考えられます。
| No. | 受け入れ基準 |
|---|---|
| 1 | 検索ボックスにキーワードを入力して検索ボタンを押すと、関連する商品一覧が表示される |
| 2 | 検索結果が0件の場合、「該当する商品はありません」というメッセージが表示される |
| 3 | キーワードに複数の単語を入力した場合、AND条件で検索される |
| 4 | 検索結果は、関連度の高い順に表示される |
このように、具体的な条件を事前に合意しておくことで、手戻りを最小限に抑え、効率的に開発を進めることが可能になります。
必要なタイミングで設計書を作成するという考え方

ユーザーストーリーと受け入れ基準によって大枠の合意は形成できますが、それだけでは実装が難しい複雑な部分もあります。そのような場合には、必要なタイミングで設計書を作成するという考え方が重要です。
アジャイル開発では、必要な情報を「ジャストインタイム」で文書化し、開発を支援します。
本章では、現場でよく利用される代表的なドキュメントをご紹介します。
| ドキュメント名 | 主な目的 | 作成タイミングの例 |
|---|---|---|
| システム構成図/ER図 | システム全体像やデータ構造の共有 | プロジェクト初期・大規模な変更前 |
| API仕様書 | チーム間のインターフェース定義 | 連携機能の開発前 |
| 画面遷移図/ワイヤーフレーム | UI/UXの合意形成 | 新規画面や機能の実装前 |
これらは一度作って終わりではなく、開発の進行や変更に合わせて更新される「生きたドキュメント」です。
つまり、アジャイル開発における設計書は固定的な成果物ではなく、必要なタイミングで作成・更新し続けるものとして扱うことが、本質的な考え方なのです。
システム構成図・ER図
システム全体の構成や、データベースのテーブル間の関係性を示すER図は、プロジェクトの全体像を把握するために有効です。特に、新しいメンバーがチームに参加した際のオンボーディングや、影響範囲の大きい機能を改修する場面で役立ちます。
システム構成図とは、サーバー・アプリケーション・データベース・外部サービスなどの要素がどのようにつながっているかを俯瞰的に示す図です。これにより、システムの仕組みを直感的に理解でき、関係者間で共通認識を持ちやすくなります。
システム構成図やER図は、あまりに細部まで書き込む必要はなく、チームが必要とするレベルの情報を簡潔に表現することが求められます。
API仕様書
フロントエンドとバックエンドでチームが分かれている場合や、外部システムとの連携が必要な場合には、API(Application Programming Interface)の仕様を明確に定義することが不可欠です。
API仕様書は、チーム間のスムーズなやり取りを支え、認識の齟齬や手戻りを防ぐための契約書のような役割を果たします。特に複数のチームや外部ベンダーが関わるプロジェクトでは、その重要性が一層高まるでしょう。
近年では Swagger(OpenAPI Specification) などのツールを活用し、仕様書からコードを自動生成したり、コードから仕様を生成したりすることで、作成やメンテナンスの効率化も進んでいます。
画面遷移図・ワイヤーフレーム
ユーザーがアプリケーションをどのように操作するかを示す画面遷移図や、各画面のレイアウトを大まかに表すワイヤーフレームも欠かせないドキュメントです。
これらはエンジニアだけでなく、デザイナーやプロダクトオーナーなど関係者全員がユーザー体験(UX)の共通イメージを持つために役立ちます。認識が揃うことで、後工程での仕様変更や手戻りを大幅に減らせます。
さらに、Figmaなどのデザインツールを用いて作成されたプロトタイプは実際に操作できるため、開発の初期段階でユーザー視点の確認が可能です。これにより齟齬を早期に発見し、効率的な開発を実現できます。
アジャイル開発に適した管理ツールとは?
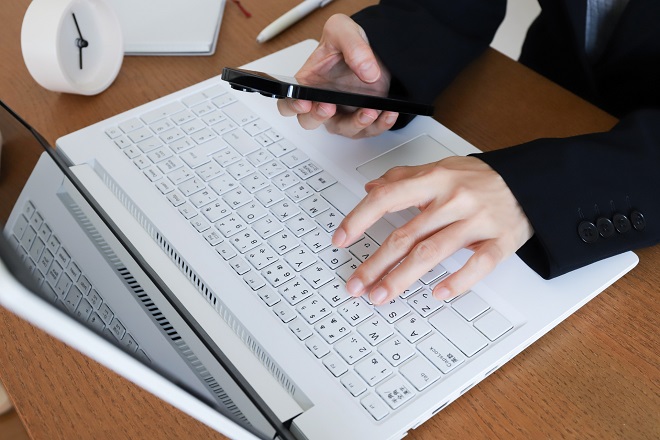
アジャイル開発では、ユーザーストーリーやタスク、必要に応じて作成される設計ドキュメントなど、様々な情報が日々生まれます。これらの情報がバラバラに管理されていると、チームの生産性やスピードが大きく低下する原因になりかねません。
そこで本章では、こうした課題を解決し、アジャイル開発を円滑に進めるために欠かせない管理ツールの活用法について解説します。
なぜツールが必要?ドキュメントとタスクの一元管理が鍵
ドキュメントはWikiツール、タスクはチケット管理ツール、といった形で情報が分散しているとどうなるでしょうか。仕様を確認するたびに複数の場所を行き来する必要があり、タスクは更新されてもドキュメントが古いまま放置されるなど、情報の齟齬が生じやすくなります。
理想的なのは、開発タスク(チケット)と、その背景にある仕様や議論の経緯(ドキュメント)が紐づき、一つの場所で一元管理されている状態です。こうすることで、誰でも最新の情報に素早くアクセスでき、チーム全体で情報の鮮度と整合性を保ちながら開発を進められます。
Lychee Redmineでアジャイル開発をもっとスムーズに
当メディアを運営する株式会社アジャイルウェアが開発・提供するプロジェクト管理ツール「Lychee Redmine」は、まさにアジャイル開発における情報の一元管理を実現するために設計されています。
Lychee Redmineは7,000社以上に導入されており、多くのチームのアジャイル開発を支えています。
Lychee Redmine がアジャイル開発をどのように支援するのか、その主な機能とメリットを以下の表にまとめました。
| Lychee Redmineの主な機能 | アジャイル開発におけるメリット |
|---|---|
| カンバン | タスクをカード形式で管理し、進捗状況を直感的に把握できます。作業の流れを「見える化」することで、ボトルネックや遅延の発生箇所を素早く発見できます。 |
| チケットとWikiの連携 | 開発タスク(チケット)に関連するWikiページを直接紐づけられるため、仕様や議論の内容を分散させずに管理できます。常に最新の情報にアクセスでき、チーム全体で認識を共有できます。 |
| ガントチャート | スプリント単位の計画だけでなく、プロジェクト全体のスケジュールやタスク間の依存関係を可視化します。短期・長期の両方の視点で計画を立てやすくなります。 |
| EVM(出来高管理) | コストと進捗を数値で測定し、計画と実績の乖離を早期に把握できます。客観的なデータに基づいて判断できるため、健全で安定したプロジェクト運営を支援します。 |
これらの機能を活用することで、ドキュメント作成や情報共有の手間を削減し、チームが本来の目的である「価値あるソフトウェアを届ける」ことに専念できる環境を構築できます。
なお、下記の関連記事ではプロジェクト管理に有効なガントチャートについて解説しています。あわせてご覧ください。
アジャイル開発でビジネスを加速しよう

アジャイル開発におけるドキュメントの考え方は、「価値を生まないドキュメントは作らず、チームの役に立つドキュメントを、適切なタイミングで、適切な量だけ作る」というものです。
ウォーターフォール開発における設計書が「指示書」だとすると、アジャイル開発におけるドキュメントは「コミュニケーションの潤滑油」です。プロダクトバックログやユーザーストーリーを起点に、必要に応じてER図やAPI仕様書などを活用することで、チームの共通認識を深め、認識のズレによる手戻りを防ぎます。
設計書に対する漠然とした不安は、役割と適切な使い方を理解することで自信へと変わります。ドキュメントを恐れるのではなく、チームを加速させるための強力なツールとして使いこなしましょう。
アジャイル開発をさらに推進するためには、ツール選びも重要です。「Lychee Redmine」なら、プロジェクト計画からタスク管理、ドキュメントの共有まで一元管理が可能です。
30日間の無料トライアルで、実際に「しなやかで強いチームづくり」を体験してみてください。
30日無料トライアルをはじめる
- 多機能ガントチャート/カンバン/バックログ/リソース管理/CCPM/レポートなど
- ・ クレジットカード登録不要
- ・ 期間終了後も自動課金なし
- ・ 法人の方のみを対象
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。



