
複数のチームが関わるプロジェクトで、「チーム間の連携がうまくいかない」「開発スピードが落ちてきた」「組織全体の見通しが悪く、何が問題なのかわからない」といった課題に直面していませんか。プロジェクトの規模が拡大するにつれて、こうした複雑な問題は多くの組織を悩ませます。
これらの課題を解決する一つの強力なアプローチが「大規模スクラム」です。本記事では、その代表的なフレームワークである「Large Scale Scrum(LeSS)」について、基本からわかりやすく解説します。LeSSの定義や原則、他のフレームワークとの違い、そして具体的な導入のポイントまでを網羅的に学ぶことで、あなたの組織に最適な開発体制を築くためのヒントが見つかるはずです。
Large Scale Scrum(LeSS)とは

LeSSの定義
Large Scale Scrum(LeSS)とは、大規模な製品開発にスクラムを適用するためのフレームワークです。単にスクラムチームの数を増やすのではなく、スクラムの原則やルールを大規模な環境で機能させることに主眼を置いています。つまり、LeSSはスクラムの精神を維持しつつ、より多くの人々が関わるプロジェクトでも効率的に、そして効果的に製品開発を進めるための道筋を示しています。
LeSSの目的は、組織の複雑さを増やさずに複数のチームが一体となって一つの製品を開発し、顧客価値を最大化することです。大規模な開発では、チーム間の情報共有や調整に多くの時間がかかりがちですが、LeSSはそうした負担を最小限に抑えることを目指します。そのため、LeSSは意図的にルールや役割の追加を抑えています。
従来のスクラムとの違い
LeSSを理解する上で重要なのは、「複数の独立したスクラムチームが存在すること」ではなく、「複数チームが連携し、1つのプロダクトに対して共通のスクラムフレームワークを適用すること」です。これは、スクラムの基本原則をチーム横断的に共有し、全チームが一体となって1つのプロダクトを開発することを意味します。
具体的には、以下の点が単一チームのスクラムと大きく異なります。
| 要素 | 単一チームのスクラム | Large Scale Scrum (LeSS) |
|---|---|---|
| プロダクトバックログ | 1つ | 全チームで共有する1つのバックログ |
| プロダクトオーナー | 1人 | 全体を統括する1人のプロダクトオーナー |
| スプリント | 1つのスプリント | 全チームが同期する1つのスプリント |
| 完成の定義 (DoD) | 1つ | 全チームで共通の1つの定義 |
| 出荷可能なインクリメント | 1つ | 全チームの成果を統合した1つのインクリメント |
このように、LeSSでは組織全体が「One Team」として機能することを目指します。これにより、部分最適化を防ぎ、プロダクト全体の価値向上に集中できるのです。
Large Scale Scrum(LeSS)を支える10の原理原則

LeSSは単なるルールの集合体ではなく、その根底に流れる10の原理原則に基づいています。これらの原則は、LeSSを実践する上での思考の軸となり、なぜそのルールが存在するかの理由の理解を助けるものです。ここでは特に重要な原則をいくつか紹介します。
原則1:Large Scale Scrumはスクラムである
LeSSの根幹は、あくまでスクラムガイドに準拠したスクラムです。スプリント、デイリースクラム、スプリントレビュー、レトロスペクティブといったイベントや、プロダクトオーナー、スクラムマスター、開発チームの役割はそのまま活かされます。そのため、スクラムの経験があるチームや組織は、その知識を土台としてLeSSへ移行が可能です。
原則2:経験ベースのプロセス管理
LeSSは、詳細な計画に固執するのではなく、透明性・検査・適応という経験的プロセス制御のサイクルを重視します。実際に取り組んで得られた事実や学びに基づき、プロセスやプロダクトを継続的に改善していく姿勢です。この原則があるからこそ、LeSSは最小限のルールで運用できます。
原則3:透明性
プロセス、進捗、課題、成果物など、開発に関わるあらゆる情報をすべての関係者に見えるようにすることが不可欠です。例えば、全チームが共有するプロダクトバックログやスプリントの状況をプロジェクト管理ツールで可視化することが挙げられます。透明性が確保されることで、チーム間の信頼関係が生まれ、迅速な問題解決や的確な意思決定ができます。
原則4:LeSSでさらに多く(More with LeSS)
これはLeSSの思想的中心となる原則です。役割、プロセス、成果物、ツールなどを意図的に少なく(Less)することで、組織の複雑さを減らし、本質的な価値創造に集中し、より多くの成果(More)を得ることを目指します。不要な管理や調整コストを削減し、柔軟性とスピードを高めるための哲学です。
原則5:製品全体思考
各チームは自分が担当する部品(コンポーネント)や機能だけでなく、常に製品全体の価値に焦点を当てる必要があります。部分的な最適化は、場合によっては全体の非効率につながることがあるからです。この原則を実践することで、チームは「自分の仕事がプロダクト全体の成功にどう貢献するのか」を常に意識し、全体最適の視点で行動するようになります。
原則6:顧客中心
開発のすべての活動は、最終的に顧客に価値を届けるために行われるべきです。LeSSでは開発チームが顧客やユーザーと直接対話し、フィードバックを得る機会を積極的に作ることが推奨されます。これにより、机上の空論ではなく、本当に顧客が求めているものを開発できる確率が高まります。
原則7:完璧を目指しての継続的改善
現状に満足せず、プロセス、製品、組織のあり方を常に改善し続ける姿勢が求められます。特に、複数のチームが関わる「全体レトロスペクティブ」といったイベントを通じて、チーム単体では解決できない組織レベルの課題を見つけ、改善していく文化を育むことが重要です。
原則8:システム思考
プロダクト開発に関わる組織やプロセス全体を一つのシステムとして捉え、そのパフォーマンスを最大化することを目指します。あるチームで起きた問題は、そのチームだけの問題ではなく、システム全体のどこかに原因があると考えます。チーム間の依存関係やボトルネックを局所的に捉えず、システム全体として解決策を探るアプローチです。
原則9:リーン思考
「ムダをなくす」というリーン生産方式の考え方もLeSSの重要な原則です。価値を生まない活動(手戻り、待機時間、過剰な書類作成など)を特定し、徹底的に排除することで、顧客に価値が届くまでの流れ(フロー)を効率化します。
原則10:待ち行列理論
多くのタスクを同時に進めると(仕掛品が多い状態)、各タスクが完了するまでの時間が長くなり、結果的に効率が落ちるという理論です。LeSSでは一度に着手する作業量を意図的に制限することで、かえって全体のリードタイムを短縮し、予測可能性を高めることを目指します。
Large Scale Scrum(LeSS)の運用方法
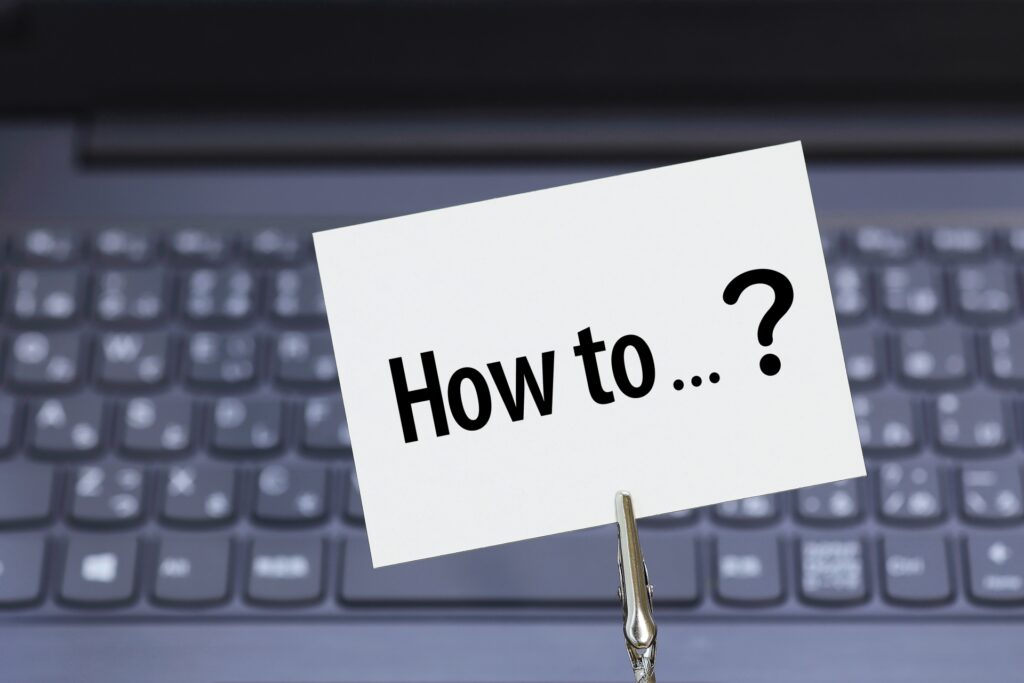
LeSSの原則を理解した上で、ここでは具体的な運用方法について解説します。チーム構成や役割、プロダクトバックログの扱い方など、実践的な側面に焦点を当てて紹介します。
チーム構成
LeSSでは、顧客に直接価値を届けられる「フィーチャーチーム」を組織の基本単位として推奨しています。
フィーチャーチームは、特定の機能(フィーチャー)の企画からリリースまでを一貫して担当するチームです。専門分野が異なる様々なスキルを持ったメンバーで構成されています。製品の企画から開発、運用まで、すべての工程を一貫して担当するため、製品全体を俯瞰できます。これにより、個々の機能が顧客にもたらす価値を深く理解し、より迅速かつ効果的な開発が可能です。
一方、従来型のスクラム開発でよく見られるコンポーネントチームは、特定の技術要素や部品(データベース、UIライブラリなど)のみを担当するチームです。コンポーネントチームは専門性を高めやすい反面、LeSSにおいてはチーム間の依存関係を生み出しやすく、開発のボトルネックとなる可能性があるため、原則として避けるべきとされています。フィーチャーを完成させるためには複数のコンポーネントチームの連携が必要となり、調整コストが増加し、結果的に開発スピードが低下してしまうためです。
フィーチャーチームを中心とした組織体制は、チームの自律性と変化への対応力を高めます。LeSSでは、こうした柔軟性のあるチーム構成を通じて、顧客価値の最大化と開発効率の向上を同時に実現することを目指しており、そのためにフィーチャーチームの構築を強く推奨しています。
プロダクトオーナーの責任範囲
LeSSでは、プロダクト全体の方向性と価値最大化に対する責任を明確にするため、プロダクトオーナーは「プロダクト全体に対して唯一責任を持つ存在」とされています。その理由は、複数のプロダクトオーナーが存在すると、責任の所在が曖昧になり、一貫性のある意思決定が難しくなるからです。
プロダクトオーナーは、以下のような重要な役割を担います。
| 役割 | 説明 |
|---|---|
| プロダクトの方向性決定 | プロダクト全体の方向性を明確にし、その価値を最大化する責任を持つ。 |
| プロダクトバックログの管理 | 全チームが共有する唯一のプロダクトバックログの優先順位を決定する。これによって、開発の方向性に一貫性を持たせられる。 |
| ステークホルダーとの連携 | 複数チームの要求やステークホルダーの意見を集約し、プロダクト全体の方針との整合性を保つ。 |
| チームとのコミュニケーション | 各チームと密に連携し、プロダクトの方向性を明確に伝えるとともに、チームとの継続的な対話を通じて、共通理解を築く。 |
プロダクトオーナーは、プロダクトの成功に向けて、一貫性と透明性をもって意思決定を行う必要があります。
プロダクトバックログの統合運用
プロダクトバックログの統合は、組織全体のベクトルを揃え、効率的な開発を促すための重要な施策です。複数のチームがそれぞれのプロダクトバックログを持った場合、組織全体の優先順位が見えにくくなり、各チームが異なる方向へ進んでしまう可能性があります。そのため、プロダクトバックログを1つに統合して組織全体の目標を明確にし、すべてのチームが同じ方向に進めるようにすることが重要です。プロダクトバックログを統合することで、資源の集中や重複開発の防止にもつながり、結果として開発効率の向上に貢献します。
LeSSとLeSS Hugeの違い
LeSSには、組織の規模に応じて2つのフレームワークが用意されています。
| フレームワーク | 対象チーム数 | 特徴 |
|---|---|---|
| LeSS | 2〜8チーム | 基本的なLeSSのフレームワーク。1人のプロダクトオーナーが全チームを統括する。 |
| LeSS Huge | 8チーム以上 | さらに大規模な開発向け。製品を「要求エリア」に分割し、エリアごとに「エリアプロダクトオーナー(APO)」を配置して、プロダクトオーナーを補佐する。 |
多くの組織では、まず基本的なLeSSから始め、組織の成長に合わせてLeSS Hugeへの移行を検討することが推奨されます。
Large Scale Scrum(LeSS)のメリット・デメリット
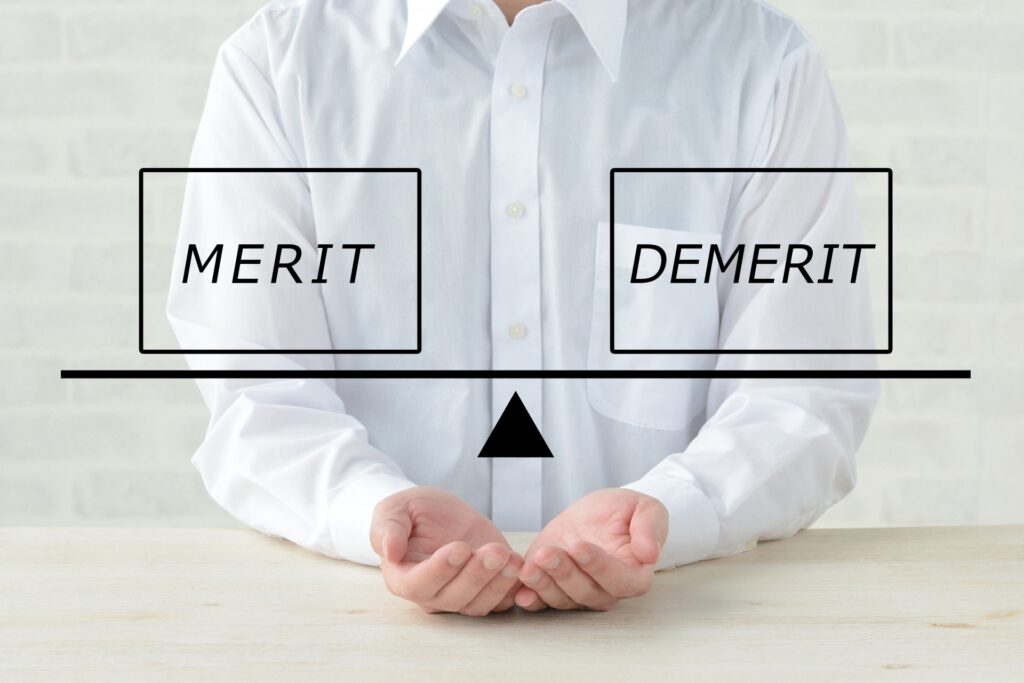
LeSSの導入を検討する上で、そのメリットとデメリットを客観的に理解しておくことが重要です。
LeSSのメリット
メリットを理解することは、LeSS導入の意思決定や、導入後の改善活動を効果的に進める上で非常に大切です。
LeSSの代表的なメリットは、以下の通りです。
| メリット | 説明 |
|---|---|
| 組織全体の透明性向上 | 1つのプロダクトバックログと同期したスプリントにより、誰が何に取り組んでいるか、プロダクト全体の進捗が明確になる。 |
| 製品全体に対する視点の共有 | 全チームが同じ目標を共有するため、部分最適化に陥らず、プロダクト全体の価値向上に貢献できる。 |
| 組織のシンプル化 | 不要な役割やプロセスを意図的に排除するため、組織構造がシンプルになり、意思決定が迅速になる。 |
| 顧客価値への集中 | プロダクトオーナーが全体に責任を持ち、1つのプロダクトバックログで優先順位を管理することで、全チームが真に価値ある機能の開発に集中できる。 |
| チームの自己組織化とオーナーシップの促進 | LeSSでは、管理者や細かな役割分担を避け、各チームが自律的に課題解決する環境が整っているため、大規模環境でも自己組織化が促進される。 |
LeSSのデメリット
LeSSには様々なメリットがある一方、デメリットもあります。デメリットを理解することは、LeSSがプロジェクトに適切かどうかを判断するために大切です。
| デメリット | 説明 |
|---|---|
| プロダクトオーナーへの負荷集中 | 唯一のプロダクトオーナーに責任とタスクが集中し、ボトルネックになる可能性がある。 |
| 導入初期の学習コストと組織変革 | LeSSの原則を理解し、従来の組織構造や文化を変えるには、相応の時間と労力が必要。 |
| チーム間の依存関係の調整 | LeSSの導入初期や移行期に、チーム間の依存調整に一定のコストがかかることもある。 |
| 高度なスキルセットの要求 | スクラムマスターには高度なファシリテーション能力が、開発者には幅広い技術スキルが求められる。 |
【比較】Large Scale Scrum(LeSS)と他のスケーリングフレームワーク

大規模アジャイルのフレームワークはLeSSだけではありません。代表的なフレームワークと比較することで、LeSSの特徴をより深く理解しましょう。
SAFe(Scaled Agile Framework)
SAFeは、リーンとアジャイルの原則をベースに、プロセスの標準化や予測可能性、そして顧客価値の継続的提供を重視します。大規模な組織でのアジャイル導入を目的としており、複数のチームを連携させ、ビジネス価値を効率的に提供することを目指します。
<SAFeの概要>
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 目的 | 大規模組織でのアジャイル導入 |
| 特徴 | 標準化されたプロセス、詳細なロードマップ、明確な役割定義 |
| 規模 | 大規模組織(50人以上~数千人) |
一方、LeSSはシンプルさと自己組織化を重視し、組織構造の変革を伴うことが一般的です。小規模から中規模の組織に適しており、より柔軟なアジャイル開発を目指します。SAFeは、大規模で複雑な組織、特に明確なプロセスと予測可能性を求める組織に適しています。
DAD(Disciplined Agile Delivery)
DADは、プロジェクトの成功を重視し、状況に応じて様々なプラクティスを適用できる柔軟性を提供します。一方、LeSSはスクラムを大規模に適用することを目指し、よりシンプルな構造を重視します。
<DADの概要>
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 目的 | ビジネス価値の迅速な提供と、プロジェクトの成功 |
| 特徴 | スクラムやカンバンなど複数の手法を統合し、柔軟かつ拡張性の高いアプローチ |
| 規模 | 小規模チームから大規模プロジェクトまで対応可能 |
DADは、既存のプロセスやツールを活用しつつ、アジャイルなプラクティスを取り入れたい組織に適しています。特に、厳格なガバナンスが必要な大規模プロジェクトや、特定のフレームワークに縛られたくない組織に有効です。
Nexus
LeSSは組織構造そのものを簡素化して大規模スクラムを実現するアプローチであるのに対し、Nexusは既存のスクラムチームに統合メカニズムを追加するアプローチです。
<Nexusの概要>
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 目的 | 複数のチームの成果を統合し、一貫性のある製品インクリメントを提供すること |
| 特徴 | スクラムを基本とし、Nexus統合チームが調整役を担う |
| 規模 | 3〜9チーム程度の開発に適している |
Nexusは、すでに基本的なスクラムプロセスが定着しており、スクラムチーム間の統合に焦点を当てたい組織に適しています。
Scrum@Scale
LeSSが大規模スクラムの原則を重視するのに対し、Scrum@Scaleはスクラムの構造を拡張し、組織全体でのスクラム導入を促進します。
<Scrum@Scaleの概要>
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 目的 | スクラムの基礎を活用して複数のチーム間の連携や相互作用に焦点を当て、組織全体の文化を変革すること |
| 特徴 | 「スケールフリーアーキテクチャ」の考え方に基づき、組織の状況に合わせて柔軟なカスタマイズが可能 |
| 規模 | チーム数に制限はなく、大規模な組織にも適用可能 |
LeSSよりも規定が少ないため、組織文化や既存のプロセスを尊重しながら、段階的にアジャイルな組織へと変革したい場合に適しています。特に、組織の自律性を重視し、現場主導での改善を促したい場合に有効です。
比較表
| LeSS | SAFe | DAD | Nexus | Scrum@Scale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 目的 | シンプルさと自己組織化を重視したアジャイル開発 | 大規模組織でのアジャイル導入 | ビジネス価値の迅速な提供と、プロジェクトの成功 | 複数のチームの成果を統合し、一貫性のある製品インクリメントを提供すること | スクラムの基礎を活用して複数のチーム間の連携や相互作用に焦点を当て、組織全体の文化を変革すること |
| 特徴 | 組織構造の変革を伴うことが多い、シンプルさを重視 | 標準化されたプロセス、詳細なロードマップ、明確な役割定義 | 複数の手法を統合し、柔軟かつ拡張性の高いアプローチ | スクラムを基本とし、Nexus統合チームが調整役を担う | 「スケールフリーアーキテクチャ」の考え方に基づき、組織の状況に合わせて柔軟なカスタマイズが可能 |
| 規模 | 2~8チーム程度 | 大規模組織(50人以上~数千人) | 小規模チームから大規模プロジェクトまで対応可能 | 3〜9チーム程度 | チーム数に制限はなく、大規模な組織にも適用可能 |
| 適した組織 | より柔軟なアジャイル開発を目指す組織 | 明確なプロセスと予測可能性を求める組織 | 既存のプロセスやツールを活用しつつアジャイルなプラクティスを取り入れたい組織、厳格なガバナンスが必要な大規模プロジェクト | スクラムチーム間の統合に焦点を当てたい組織 | 組織文化や既存のプロセスを尊重しながら段階的にアジャイルな組織へと変革したい組織 |
Large Scale Scrum(LeSS)導入のポイント

LeSSの導入は、単に新しいプロセスを導入することではありません。成功のためには、組織文化の変革も伴う大きな挑戦です。ここでは、導入を成功に導くための重要なポイントを紹介します。
組織の現状と課題を把握する
最初に行うべきは、現状分析です。「なぜ、スクラムをスケールさせる必要があるのか」を自問し、現在の開発プロセスにおける具体的な課題(例:リリース遅延、品質問題、チーム間の対立など)を明確に定義します。目的が曖昧なまま導入を進めても、効果は得られません。
関係者と合意形成を図る
LeSSの導入は、開発チームだけでなく、マネジメント層、ビジネスサイド、人事部門など、多くの関係者を巻き込みます。導入の目的、期待される効果、そして役割や責任範囲の変更といった変化について、事前に丁寧に説明し、関係者からの理解と協力を得ることが不可欠です。
組織全体でトレーニングを受ける
LeSSの原則やプラクティスについて、関係者全員が共通の理解を持つことが成功の鍵です。LeSSの公式トレーニングに参加したり、経験豊富なLeSSコーチから支援を受けたりすることは、導入をスムーズに進める上で非常に有効です。
継続的に改善する
一度に完璧な導入を目指すのは現実的ではありません。まずは小規模な単位でLeSSを試行し、そこで得られた学びや課題を「全体レトロスペクティブ」などで共有します。そして、組織の状況に合わせて少しずつプロセスを改善し、適用範囲を広げる反復的なアプローチが推奨されます。
LeSS運用を支援するツールを選定する
LeSSは特定のツールに依存しませんが、複数チームの作業を可視化し、透明性を確保するために適切なツールは強力な助けとなります。特に、全チームで共有する1つのプロダクトバックログを効率的に管理できる、Lychee Redmineのようなプロジェクト管理ツールの活用は、多くの組織で有効です。
まとめ:Large Scale Scrum(LeSS)で大規模スクラムを成功に導こう

本記事では、大規模スクラムフレームワークであるLeSSについて、その定義から10の原理原則、具体的な運用方法、そして導入のポイントまでを解説しました。
LeSSは、単なる開発手法ではなく、「More with LeSS(より少ないもので、より多くを)」という哲学に基づき、組織のあり方そのものにシンプルさと自己組織化をもたらすアプローチです。複数チームでの開発がもたらす複雑さに悩んでいるなら、LeSSの考え方はその状況を打破するための手段となるでしょう。
プロジェクト管理をサポートするツールとして、Lychee Redmineがおすすめです。LeSSの導入と合わせて、プロジェクト全体の可視化と効率化を強力に支援します。Lychee Redmineは30日間の無料トライアルを提供しています。ご興味のある方はぜひご利用いただき、使いやすさをご体験ください。
30日無料トライアルをはじめる
- 多機能ガントチャート/カンバン/バックログ/リソース管理/CCPM/レポートなど
- ・ クレジットカード登録不要
- ・ 期間終了後も自動課金なし
- ・ 法人の方のみを対象
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。




