
「プロジェクトがなぜか上手く進まない」
「次から次へと発生する問題に、どう対処すれば良いのかわからない」
プロジェクトの責任者として、このような悩みを抱えている方は少なくありません。その漠然とした不安の要因は、プロジェクト内に存在する「課題」が適切に管理されていないことに起因している可能性があります。
本記事では、プロジェクト管理における課題の正しい定義から、具体的な原因分析、解決策までを網羅的に解説します。自己流の管理から脱却し、プロジェクトを成功に導くための体系的な知識と、課題管理表やツールの活用といった実践的な手法を身につけましょう。
プロジェクト管理の「課題」とは

プロジェクトを円滑に進めるためには、まずチーム内で「課題」という言葉の認識を合わせることが不可欠です。課題とは、単に発生した「問題」そのものではなく、「問題を解決するために、具体的に取り組むべきこと」を指します。
つまり、現状(問題が発生している状態)と、あるべき姿(問題が解決された状態)のギャップを埋めるための、意図的なアクションや検討事項が「課題」なのです。「課題」の定義を共有することで、チームは同じ方向を向いて具体的な解決策の実行に進めます。
「課題」「問題」「リスク」「タスク」の違い
プロジェクトの現場では、「課題」と混同されがちな言葉がいくつかあります。特に「問題」「リスク」「タスク」との違いを明確に理解し、使い分けることが、チーム内の円滑なコミュニケーションの基盤となります。
認識のズレは対応の遅れや手戻りの原因に直結するため、以下の表を参考にチーム全体で共通認識を持ちましょう。
| 用語 | 意味 | 具体例 |
|---|---|---|
| 問題 (Problem) | プロジェクトの「あるべき姿」と「現状」の間に生じた好ましくないギャップや事象 | スケジュールが計画より3日遅れている |
| 課題 (Issue) | 「問題」を分析し、解決のために検討・実行すべき具体的なアクションやテーマ | 遅延の原因を特定し、リカバリー計画を策定する必要がある |
| リスク (Risk) | 将来発生する可能性のある、プロジェクトに影響を与える不確実な事象 | 主要メンバーが急に退職するかもしれない |
| タスク (Task) | 「課題」を解決するために行う、個別で具体的な作業 | 関係者を集めて遅延原因分析会議を開催する |
これらの用語を正しく使い分けることで、発生した問題を迅速に共有し、それを課題として設定し、具体的なタスクに落とし込んで担当者を割り当てるまでの流れをスムーズに進められます。
課題管理とタスク管理の違い
課題管理は、プロジェクト進行中に発生した「解決すべき問題や懸念事項」を記録し、原因と解決策を明確にして解決までを追う管理手法です。目的は、進行を妨げる要因を早期に解消することにあります。
一方、タスク管理は、計画された作業に対して期限と担当者を設定し、進捗を管理する手法です。目的は、計画通りに作業を遂行し、スケジュールを守ることにあります。
課題管理は問題を解決することを目的とし、タスク管理は作業を遂行することを目的としています。
PMBOKにおける課題管理の定義と重要性
「PMBOK(Project Management Body of Knowledge)」とは、プロジェクト管理に必要な知識や手法を体系的に整理した国際標準のフレームワークです。
PMBOKでは、課題は「プロジェクトに影響を与える可能性のある、現在進行中の論点または問題」と定義され、リスクとは明確に区別されます。リスクが「未来」の不確実性であるのに対し、課題は「現在」発生している事象を指すのです。
PMBOKでは、発生した課題を「課題ログ(Issue Log)」と呼ばれる文書に記録し、追跡・管理することが推奨されています。これは、課題を見える化し、誰が、いつまでに、どのように対応するのかを明確にすることで、課題の放置や対応漏れを防ぐための重要なプロセスです。
課題ログの運用は、プロジェクトの健全性を保ち、ステークホルダーへの透明性を確保する上で不可欠とされています。
なお、PMBOKについては以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
プロジェクト管理で起こりがちな5つの課題とその対策

どのようなプロジェクトでも、共通して発生しやすい典型的な課題があります。それは規模や業種を問わず、経験豊富なプロジェクトマネージャーでさえ避けるのが難しいものです。
以下では、多くのプロジェクトマネージャーが直面する5つの代表的な課題を取り上げます。それぞれの課題について、「具体的な原因」「プロジェクトへの影響」、そして「明日から使える実践的な解決策」をあわせて解説します。
ご自身のプロジェクト状況と照らし合わせながら、解決のヒントを見つけてください。
1. コミュニケーション不足による情報伝達の乱れ
リモートワークの普及もあり、チーム内のコミュニケーション不足は手戻りや認識のズレなど、深刻な問題を引き起こす主な原因となっています。
情報共有のルールが曖昧だったり、誰に何を確認すれば良いか不明確だったりすると、作業の重複や意思決定の遅延につながります。この課題を解決するには、コミュニケーションの仕組みづくりが不可欠です。
| 解決策 | 具体的なアクション |
|---|---|
| コミュニケーション計画の策定 | 誰が、誰に、何を、いつ、どのように伝えるかを定義し、RACIマトリックスなどで責任の所在を明確化する |
| 定例会議の質の向上 | 会議の目的と議題を事前に共有し、議事録を作成して決定事項と次のアクションを必ず記録する |
| ツールの活用 | ビジネスチャットツール(Slack, Teamsなど)やプロジェクト管理ツールを導入し、情報共有の場を一元化する |
2. ゴールの曖昧さによるスコープクリープ
プロジェクトの最終的なゴールや目的が曖昧なままスタートすると、関係者から次々と追加の要望が出てきてしまい、ずるずると作業範囲が拡大してしまう「スコープクリープ」が発生しやすくなります。
スコープクリープは、予算超過や納期遅延の直接的な原因となり、プロジェクト失敗の大きな要因となります。 スコープクリープを防ぐためには、プロジェクト開始時点での明確なゴール設定が何よりも重要です。
| 解決策 | 具体的なアクション |
|---|---|
| SMART原則に基づく目標設定 | 目標を「Specific(具体的)」「Measurable(測定可能)」「Achievable(達成可能)」「Relevant(関連性)」「Time-bound(期限)」の5つの観点で設定し、誰が見ても明確なゴールにする |
| WBSの作成 | WBS (Work Breakdown Structure) を用いて、プロジェクトの成果物を達成するために必要な作業を階層的にすべて洗い出し、作業範囲を明確に定義する |
| ステークホルダーとの合意形成 | 設定したゴールとWBSを元に、プロジェクトで「やること」と「やらないこと」を関係者全員で合意し、文書として残す |
3. 不適切なリソース配分による作業停滞
「このタスクは、誰が担当するのが最適か?」という問いに対する答えを誤ると、プロジェクトの遅延や品質低下に直結します。 メンバーのスキルや経験、現在の負荷状況を考慮せずにタスクを割り振ると、作業が滞ったり、アウトプットの質が低下したりする原因となります。
特に優秀なメンバーにタスクが集中し、バーンアウト(燃え尽き症候群)を引き起こすケースも少なくありません。主な対策は以下の通りです。
| 解決策 | 具体的なアクション |
|---|---|
| スキルマトリックスの作成 | チームメンバー各自のスキルや経験、資格などを一覧表にして可視化し、タスクの要求スキルとマッチングさせる |
| リソース計画と平準化 | 各メンバーの負荷状況を把握し、特定の時期や個人に作業が集中しないようにタスクを再配分(リソース平準化)する |
| 定期的な1on1ミーティング | メンバーと定期的に面談し、キャリアプランや挑戦したい業務内容をヒアリングすることで、モチベーションやスキルを考慮したタスクの割り当てが可能になる |
4. リスク管理の欠如によるトラブル対応の後手化
「きっと大丈夫だろう」という楽観的な見通しは、プロジェクト管理において最も危険な考え方の一つです。事前に起こりうる問題を予測し、対策を立てておく「リスク管理」を怠ると、予期せぬトラブルが発生した際に対応が後手に回り、プロジェクトに深刻なダメージを与えます。
リスク管理は、将来の課題を未然に防ぐための重要な活動です。
| 解決策 | 具体的なアクション |
|---|---|
| リスクの洗い出し | ブレインストーミングなどを通じて、プロジェクトに影響を与えうる潜在的なリスク(技術的、人的、外部環境など)をすべて洗い出す |
| リスクの評価 | 洗い出した各リスクについて、「発生確率」と「影響度」の2軸で評価し、対応の優先順位を決定する |
| リスク登録簿の作成と管理 | すべてのリスクとその評価結果、具体的な対応策(回避・軽減・移転・受容)、そして担当者を「リスク登録簿」に整理して管理し、定期的に更新・見直す |
5. スケジュール管理の精度不足
プロジェクトのスケジュール作成において、個々のタスクの見積もりが甘かったり、タスク間の依存関係を見落としたりすると、最終的に致命的な納期遅延につながります。
一つのタスクの遅れが、ドミノ倒しのように後続のタスク全体に影響を及ぼすことは珍しくありません。精度の高いスケジュール管理は、プロジェクト成功の鍵となります。
| 解決策 | 具体的なアクション |
|---|---|
| 精度の高い見積もり | 過去の類似プロジェクトのデータや専門家の意見を参考に、現実的な工数を算出します。加えて、楽観的・標準的・悲観的な3つのシナリオで見積もる「三点見積もり」を活用すると、予測の信頼性が高まります。 |
| クリティカルパス分析 | タスク間の依存関係を整理し、プロジェクト全体の期間を左右する最重要タスク群(クリティカルパス)を特定します。その上で、遅延を防ぐために重点的な管理を行います。 |
| 進捗の可視化 | ガントチャートなどのツールを使い、計画と実績の差異を常に把握します。遅延の兆候を早期に発見し、必要な対策を迅速に講じられる体制を整えます。 |
抜け漏れを防ぐ「課題管理表」の作り方

発生した課題を確実に解決まで導くためには、課題を一元管理するための「課題管理表」が不可欠です。
課題管理表は、課題の抜け漏れを防ぎ、対応状況をチーム全体で共有するための最も基本的で強力なツールです。ExcelやGoogleスプレッドシートでも簡単に作成できるため、以下の項目を参考に、ご自身のプロジェクト用の管理表を作成してみてください。
| 管理項目 | 内容説明 | 例 |
|---|---|---|
| 管理番号 | 課題を識別するための一意の番号 | No.001 |
| 課題名 | 課題の内容が一目でわかる簡潔なタイトル | 開発環境へのアクセス遅延問題 |
| 課題詳細 | 発生している問題の具体的な内容、背景、影響範囲などを記述 | 〇〇サーバーへの接続に通常3秒のところ、30秒以上かかっている |
| 発生日 | 課題が認識された日付 | 2025/05/15 |
| 起票者 | 課題を最初に報告した担当者名 | 鈴木 |
| 担当者 | 課題解決の主担当者名 | 佐藤 |
| 優先度 | 対応の緊急性や重要度を設定(例:「高」「中」「低」) | 高 |
| 期限 | 課題解決の目標日 | 2025/05/20 |
| ステータス | 課題の進捗状況(例:「未着手」「対応中」「保留」「完了」) | 対応中 |
| 対応方針・進捗 | 解決策や対応履歴を時系列で記録 | 5/16 ネットワーク担当に原因調査を依頼 |
課題管理表をチームで共有し、定例会議などで定期的にレビューすることで、課題への対応状況が明確になり、プロジェクトを安定的に推進できます。
課題解決の基本ステップ【実務フロー形式】

課題を発見してからクローズするまでの一連の流れを、体系的なプロセスとして確立しておくことで、場当たり的な対応を防ぎ、着実に問題を解決できます。
以下では、どのような課題にも応用できる、普遍的で実践的な5つのステップをご紹介します。
課題の発見と記録
チームの誰もが課題に気づいたときに、すぐに報告・記録できる仕組みが重要です。日々の朝会やチャットツールでの報告を推奨し、些細なことでも「問題の兆候」として捉える文化を育成します。
発見された課題は、前述の「課題管理表」に速やかに記録し、チーム全体で可視化することが最初のステップです。
原因の分析と特定
記録された課題に対して、「なぜそれが起きたのか?」を深掘りし、根本的な原因(真因)を特定しましょう。表面的な事象だけに対処しても、同じ問題が再発する可能性があります。
「なぜ」を5回繰り返す「なぜなぜ分析」のようなフレームワークを活用すると、問題の本質にたどり着きやすくなります。
解決策の立案
真因が特定できたら、それを解消するための具体的な解決策を複数検討します。効果、コスト、実現可能性などを考慮して最適な解決策を選択し、誰が・何を・いつまでに行うのか、具体的な「タスク」に分解して計画を立てます。
この計画については、関係者全員の合意を得ることが重要です。
対策の実行と進捗管理
計画に基づいて、担当者は解決策を実行します。プロジェクトマネージャーは課題管理表のステータスを更新しながら、対策が計画通りに進んでいるかを定期的に確認します。
進捗が思わしくない場合は、その原因を探り、計画の見直しや追加のリソース投入などのサポートを行いましょう。
ふりかえりとナレッジ化
課題が解決されたら、課題管理表のステータスを「完了」に変更します。
しかし、ここで終わりではありません。なぜその課題が発生したのか、今回の対応が適切だったかどうかなどをチームでふりかえり、得られた教訓をナレッジとして蓄積します。
この積み重ねが、組織全体のプロジェクト管理能力を向上させるのです。
プロジェクト全体で課題管理を徹底するには

課題管理をスムーズに行うためには、基盤となるプロジェクト管理全体の質を高めることが重要です。以下では、プロジェクト全体で課題管理を徹底するためのポイントをご紹介します。
PMOの活用(中規模以上の組織向け)
より大規模な組織や、複数のプロジェクトを運営している企業では、個々のプロジェクトマネージャーだけでは解決できない課題が発生します。
そこで重要な役割を担うのが「PMO(Project Management Office)」です。PMOは、プロジェクトを俯瞰的な視点から支援・管理する専門組織であり、課題管理においても以下のような重要な役割を果たします。
- 課題管理プロセスの標準化:全社で統一された課題管理表のテンプレートや運用ルールを策定し、管理品質のばらつきを防ぐ
- 横断的な課題の解決:複数のプロジェクトにまたがる課題(例:特定部門のリソース不足など)を特定し、部門間の調整や経営層へのエスカレーションを行う
- ナレッジマネジメント:各プロジェクトで発生した課題と解決策を集約・分析し、組織全体の教訓として蓄積・共有する
- ツール導入と定着支援:全社的なプロジェクト管理ツールの選定・導入を主導し、利用が定着するように研修やサポートを提供する
PMOの機能は、組織の成熟度に応じて「支援型」「管理型」「指示型」などに分けられますが、いずれのタイプも組織全体のプロジェクト遂行能力を高める上で不可欠な存在です。
管理手法の標準化やリソースの最適化、経営層との橋渡し役を担うことで、プロジェクトの成功確率を高めます。
課題管理を効率化するプロジェクト管理ツールの導入
ExcelやGoogleスプレッドシートでの管理には、更新の手間や同時編集の難しさ、属人化といった限界があります。
一方、専用のプロジェクト管理ツールを導入することで、情報の一元化、リアルタイムな進捗共有、コミュニケーションの円滑化が実現し、管理業務の大幅な効率化が可能です。
市場には数多くのプロジェクト管理ツールがありますが、自社に合わないツールを選んでしまうと、かえって業務が煩雑になることもあります。ツール選びで失敗しないために、以下の3つのポイントを必ず確認しましょう。
| 選定ポイント | 確認すべきこと |
|---|---|
| チームの規模と使い方 | 利用人数やプロジェクトの特性に合った料金プランや機能があるか ITリテラシーが高くないメンバーでも直感的に使えるか |
| 既存ツールとの連携 | すでに社内で利用しているチャットツールやストレージサービス、他の業務システムと連携できるか |
| サポート体制 | 導入時のトレーニングや、利用中に問題が発生した際の問い合わせ対応など、ベンダーのサポート体制は手厚いか |
プロジェクト管理の課題を解消!Lychee Redmineでシンプル&スムーズに
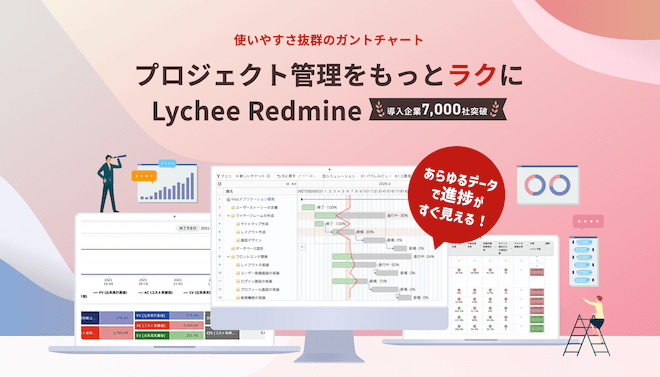
「Lychee Redmine」は、導入実績が『7,000』社を突破したクラウド型の工程管理ツールです。以下のような機能で、プロジェクト管理の課題解決を強力にサポートします。
- 課題・工数・WBS・スケジュールの一元管理
- ガントチャートによる進捗可視化
- チーム内の情報共有を強化するコメント機能
- プロジェクト横断の集計・分析機能
直感的に操作できるシンプルなUIと、現場の実務に即した豊富な機能で、課題管理の煩雑さを解消します。
有料プランでは、フリープランでは使えない高度な機能も利用可能です。30日間の無料トライアルもご用意していますので、この機会にぜひお試しください。
| プラン | 月額料金 | 利用機能 |
| フリー | 無料 |
|
| スタンダード | 900円 |
|
| プレミアム | 1,400円 |
|
| ビジネス[無料トライアルはこちらをお試しできます] | 2,100円 |
|
課題管理を制する者がプロジェクトを制す

本記事では、プロジェクト管理における「課題」の定義から管理手法、ツール活用、PMOの役割までを解説しました。課題管理は単なる問題対応ではなく、現状把握やリスク予防、チームを成功に導く戦略的な活動です。
まずは「問題」「課題」「タスク」の定義をチームで共有し、小さなプロジェクトから課題管理表の運用を始めてみてください。その一歩が成功への大きな力になります。
さらに効率化を目指すなら、「7,000社以上」が導入する「Lychee Redmine」がおすすめです。課題・工数・WBS・スケジュールの一元管理と進捗の見える化で、生産性を飛躍的に向上できます。30日間の無料トライアルもぜひお試しください。
30日無料トライアルをはじめる
- 多機能ガントチャート/カンバン/バックログ/リソース管理/CCPM/レポートなど
- ・ クレジットカード登録不要
- ・ 期間終了後も自動課金なし
- ・ 法人の方のみを対象
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。



