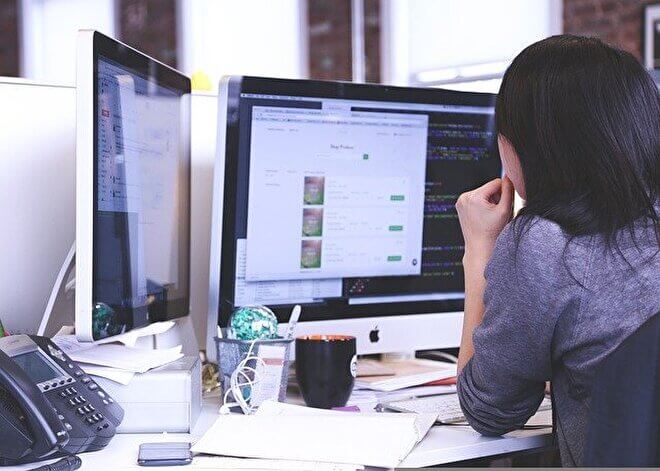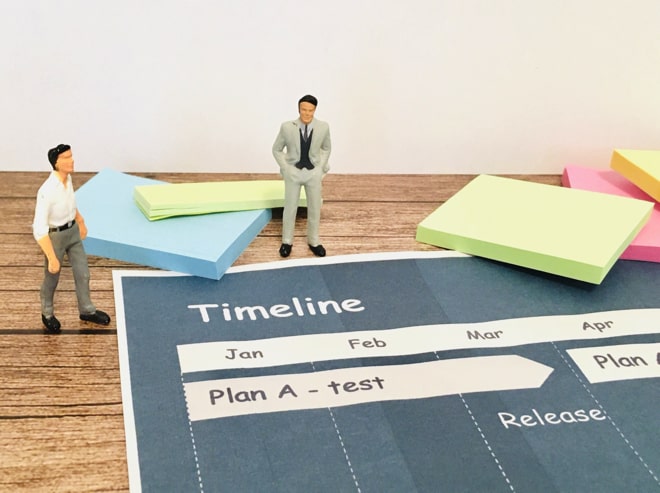システム開発プロジェクトにおいて、「要件定義でまた失敗するかもしれない」「今の進め方で本当に大丈夫だろうか」といった不安を感じた経験はありませんか。要件定義はプロジェクトの成功を左右する重要な工程でありながら、多くのプロジェクトで失敗の原因となることが少なくありません。
本記事では、システム開発における要件定義の典型的な失敗事例を詳しく分析します。さらに、失敗事例の原因を深掘りし、プロジェクトで実践できる具体的な対策までを網羅的に解説します。
本記事を参考に、要件定義の失敗を未然に防ぎ、プロジェクトを成功に導くためのポイントを押さえましょう。
要件定義はなぜ失敗するのか

要件定義は、システム開発の全工程の中で最上流に位置するプロセスです。本プロセスで作られる要件定義書は、家を建てる際の設計図に相当します。
もし設計図が曖昧であったり間違いがあったりすれば、後の工程すべてに悪影響が及び、最終的に完成する家は欠陥だらけになりかねません。システム開発も同様で、要件定義の失敗は後工程での手戻りや仕様変更を多発させる原因となるため、注意が必要です。
一般的に、開発の後工程になるほど修正コストは大幅に増大すると言われています。
要件定義が失敗しやすい原因は一つではなく、コミュニケーションや技術、プロセス、関係者のマインドセットといった複数の要因が複雑に絡み合っています。
要件定義の代表的な失敗事例5選
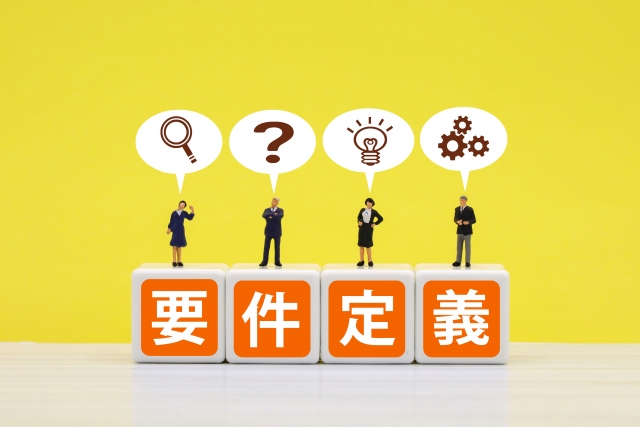
本章では、要件定義で起こりがちな典型的な失敗事例を5つのパターンに分類して紹介します。ご自身の経験と照らし合わせながら、なぜこうした問題が起こるのかを考えてみましょう。
多くの失敗は、本章で紹介するパターンのいずれか、あるいは複合形に当てはまります。
失敗事例1:認識の齟齬による曖昧な要件定義
依頼者と開発者の間でシステムの完成イメージが共有されないままプロジェクトが進行してしまう、典型的かつ頻繁に見られる失敗パターンです。「こんなはずじゃなかった」といった結果を招き、大規模な手戻りが発生します。
原因:コミュニケーション不足と行間に頼った定義
失敗の根本原因は、コミュニケーションの質と量の不足にあります。依頼者からの「良い感じでお願いします」「ユーザーが使いやすいように」といった曖昧な言葉を、開発者が「こういうことだろう」と善意で解釈して進めてしまうケースです。
実際には、両者が思い描く「良い感じ」は異なっており、プロトタイプやテストの段階でそのズレが明らかになります。背景には、形式的な打ち合わせのみで十分と考えたり、議事録に明記されていない内容を前提とする文化が存在します。
結果的に当初の計画にはなかった手戻り作業が多発し、工数が想定よりも膨れ上がる事態に陥りかねません。
対策:UMLやプロトタイプで認識の見える化を徹底する
認識の齟齬を防ぐには、言葉だけに頼らず、誰が見ても同じ解釈ができる形でコミュニケーションを取ることが不可欠です。精神論に頼るのではなく、具体的なツールや手法を活用して、システムの全体像を「見える化」しましょう。
結果的に、関係者全員が同じイメージを共有しながら議論を進められます。
| 対策手法 | 目的 | 主なツール・成果物 |
|---|---|---|
| 業務フロー図の作成 | 現状の業務プロセスと、システム化後の理想のプロセスを可視化する。 | BPMN(Business Process Model and Notation)を用いたフロー図、Miro、Lucidchart |
| UMLによるモデリング | システムの機能やデータの流れ、構造を標準化された図で表現する。 | ユースケース図、アクティビティ図、シーケンス図、クラス図など |
| ワイヤーフレーム作成 | 画面のレイアウトや要素の配置を簡易的な線画で作成し、操作性を確認する。 | Figma、Adobe XD、Cacoo、PowerPoint |
| プロトタイピング | 実際に操作できる試作品(プロトタイプ)を作成し、早期にユーザーからのフィードバックを得る。 | Prott、InVision、Figma |
| MVP開発 | 必要最小限の機能を持つ製品(Minimum Viable Product)を早期にリリースし、市場の反応を見ながら改善する。 | – |
失敗事例2:スコープクリープによるプロジェクトの崩壊
スコープクリープとは、プロジェクトの途中で次々と仕様の変更や機能の追加が発生し、当初定めた要件(スコープ)が拡大していく現象です。小さな変更の積み重ねが、気づいた時にはプロジェクト全体を脅かす大きな問題となり、納期遅延、予算超過、品質低下の直接的な原因となりかねません。
原因:変更管理プロセスの欠如と安易な受諾
スコープクリープが発生する最大の原因は、変更要求に対する明確なルール(変更管理プロセス)が存在しないことです。依頼者から「ついでにこの機能も追加してほしい」といった要望が出た際に、プロジェクトマネージャーがその影響を定量的に評価せず、「わかりました」と安易に受け入れてしまうことから始まるケースが一般的です。
背景には、「依頼者の要望に応えたい」といった善意や、「断ったら関係性が悪くなるかもしれない」といった懸念が存在します。しかし、明確なルールがないまま変更を受け入れ続けると、プロジェクトのコントロールが効かなくなり、最終的には誰にとっても望ましくない結果を招くことになります。
対策:変更管理ルールを定めて影響を定量的に評価する
スコープクリープを防ぐためには、プロジェクト開始前に関係者全員で「変更管理プロセス」に合意しておくことが重要です。
これは、変更を一切受け付けないということではありません。変更要求を正式なプロセスに乗せて影響を客観的に評価し、関係者が納得した上でスコープの変更を判断するための仕組みです。
| 変更管理プロセスのステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 変更要求の提出 | 変更を希望する者は、所定の「変更要求書」に内容や理由を記載して提出する。 | 口頭での依頼は受け付けず、文書化して記録を残します。 |
| 2. 影響分析 | プロジェクトチームが、変更がスケジュール、コスト、品質、リスクに与える影響を分析する。 | 「変更には追加で20人日の工数と50万円の費用が必要です」のように定量的に示します。 |
| 3. 変更管理委員会の開催 | プロジェクトマネージャー、依頼者代表、主要なステークホルダーで構成される委員会で、影響分析の結果を基に審議する。 | 変更を実施するか、代替案を検討するか、あるいは却下するかを正式に決定します。 |
| 4. 承認・却下の通知 | 決定事項を関係者全員に通知し、承認された場合はプロジェクト計画書を更新する。 | 決定の経緯を議事録に残し、透明性を確保します。 |
さらに、すべての要件を同列に扱わないために、MoSCoW分析などの手法で優先順位を付けることも重要です。
| 優先度 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| Must | 必ず実現すべき要件 | ないとシステムが成り立たない、または法的に必須の要件。 |
| Should | 実現すべき要件 | Mustほどではないが、非常に重要度が高く、代替手段がない要件。 |
| Could | 実現すると良い要件 | あると便利だが、なくてもシステムの価値を大きく損なわない要件。 |
| Won’t | 今回は見送る要件 | 重要度が低い、または次期リリースで検討すべき要件。 |
失敗事例3:技術的検討不足による実現性の見誤り
AIやIoT、ブロックチェーンといった最新技術を活用するプロジェクトで起こりがちな失敗パターンです。「技術的に可能だろう」といった希望的観測や不十分な調査のままプロジェクトを開始し、開発途中で技術的な壁にぶつかり、計画の大幅な見直しやプロジェクトの中止に追い込まれます。
原因:技術への過信とフィジビリティスタディの軽視
上記の失敗は、ビジネスサイドの「こうしたことを実現したい」といった夢と、技術サイドの「実現可能か」といった現実の間に大きなギャップがある場合に発生します。例えば、AIで画像認識システムを作る際に、AIモデルの学習に必要となる大量かつ高品質なデータが用意できないといったケースが典型です。
また、開発チームに当該技術の専門家がいないにもかかわらず、表面的な知識だけで「できる」と判断してしまうことも原因の一つです。技術的な実現可能性調査を軽視した結果、後になって取り返しのつかない問題が明らかになることもあります。
対策:PoCの実施と専門家の活用
技術的な不確実性が高いプロジェクトでは、本格的な開発に着手する前に、PoC(Proof of Concept:概念実証)の実施が不可欠です。PoCは、核となる技術が本当に実現可能かどうかを小規模な環境で検証する活動です。
| PoCの主な検証項目 | 具体例 |
|---|---|
| 技術的実現性 | ・AIモデルの認識精度が目標値(例:99%)に達するか ・特定のAPIが期待通りのパフォーマンスを発揮するか |
| 効果の検証 | ・技術を導入すると、本当に業務効率が改善されるか ・コスト削減効果は見込めるか |
| 課題の洗い出し | ・本格導入に向けて、どのような技術的・運用的な課題が存在するか ・必要なデータはどのような形で収集・加工すべきか |
また、社内に専門知識を持つ人材がいない場合は、ためらわずに外部の専門家(技術顧問、コンサルタントなど)の力を借りるべきです。初期のわずかな投資が、後の大きな失敗を防ぐことにつながります。
失敗事例4:発注側の丸投げによる大幅な手戻り発生
特にシステム開発の発注に慣れていない企業で起こりがちな失敗です。「専門家である開発企業に任せておけば大丈夫だろう」と考え、要件定義を「丸投げ」してしまいます。
その結果、自社の複雑な業務プロセスや暗黙のルールが反映されず、完成したシステムが現場で使われなくなるという事態を招きます。
原因:当事者意識の欠如
システム開発は、製品を購入するのとは異なります。依頼者と開発者が協力して、一つのものを創り上げるプロジェクトです。
失敗の根本原因は、発注者側に「自分たちのシステムを自分たちが主体となって作る」といった当事者意識が欠如していることにあります。
「ITのことはわからない」「普段の業務が忙しいから」といった理由で、開発企業からのヒアリングに十分な時間を確保せず、レビューも実施しない場合があります。しかし、自社の業務を理解しているのは発注者自身であり、知識が提供されなければ、開発会社は一般的な業務を想定してシステムを作るしかありません。
対策:共同ワークショップの開催とビジネスアナリストの設置
丸投げを防ぐには、発注側と開発側が物理的に同じ場所に集まり、一体となって要件を定義する場を設けることが効果的です。その代表的な手法が共同ワークショップです。
以下に、共同ワークショップの例(1日間)をまとめました。
| 行程 | 内容 |
|---|---|
| 午前 (As-Is分析) |
|
| 午後 (To-Be設計) |
|
また、両者の橋渡し役として、ビジネスアナリストと呼ばれる専門職をチームに加えることも有効です。ビジネスアナリストは、依頼者の業務を深く理解し、それをシステムの要件に落とし込むスキルを持っています。
もし専門の担当者を置けない場合でも、プロジェクトマネージャーが役割を意識的に担うことが重要です。
失敗事例5:部門間の連携不足が生むシステムの分断
全社的な基幹システムや、複数の部署が関わる大規模なシステム開発で起こりやすい失敗です。各部署が自部門の利益や都合を優先する「部分最適」に走り、システム全体としての整合性や利便性が損なわれてしまいます。
原因:全体最適視点の欠如と組織のサイロ化
問題の根底には、プロジェクト全体の成功よりも自部門の都合を優先するセクショナリズムや、部署間で情報が共有されない組織のサイロ化があります。例えば、営業部門は「もっと詳細な顧客情報を入力させたい」と要求し、経理部門は「入力項目はシンプルにしてほしい」と主張するなど要件が対立します。
プロジェクトを推進する強力なリーダーシップや部門間の調整機能が働かないと、こうした対立は解決されません。結果として、データの二重入力が発生したり、部門間でデータの整合性が取れなくなったりと、システム全体の価値を大きく損ないます。
対策:部門横断チームの組成とコミュニケーション計画の策定
問題を解決するには、組織的なアプローチが不可欠です。まず、関係する各部署から責任と権限を持つ担当者を選出し、部門横断的なプロジェクトチームを組成します。彼らは自部門の代表であると同時に、プロジェクト全体の成功に責任を負うメンバーです。
さらに、誰が、いつ、何を、どのような形でコミュニケーションするのかを定めたコミュニケーション計画を策定し、関係者全員で共有します。情報の伝達漏れや認識の齟齬を防ぎ、組織的な連携を促進します。
要件定義を成功に導く5つのコツ

前章で紹介した失敗事例から得られる教訓を、プロジェクトを成功へ導くための5つの実践的なコツとしてまとめました。これらのコツを意識することで、要件定義の質を高めることができます。
対策1:コミュニケーションを仕組み化する
「密に連携する」といった精神論だけでは、コミュニケーションは改善しません。以下を参考に、誰がいつ参加しても円滑に情報共有ができる仕組みを構築しましょう。
| コミュニケーションの仕組み | 目的 | 頻度・ルールの例 |
|---|---|---|
| デイリースタンドアップ | チーム内の進捗、課題、予定を毎日短時間で共有し、問題の早期発見を促す。 | 毎朝15分間、定時に実施。 |
| 週次レビュー会議 | 依頼者やステークホルダーにデモを見せ、フィードバックを得る。 | 週に1回、1時間程度。 |
| コラボレーションツール | 議論の経緯や決定事項、資料などを一元管理し、透明性を確保する。 | ConfluenceやNotionで議事録や仕様書を管理。 SlackやTeamsで日常的なやり取りを行う。 |
| 共通言語の定義 | プロジェクト内で使われる用語の定義をまとめた「用語集」を作成する。 | プロジェクト初期に作成し、随時更新する。 |
対策2:要件定義書の曖昧さをなくす
要件定義書は、プロジェクト関係者全員が参照する「憲法」とも言える存在です。誰が読んでも解釈に差が生じないよう、曖昧さを徹底的に排除する必要があります。
テキストだけでなく、視覚的なモデルを積極的に活用しましょう。
特に見落とされがちなのが非機能要件です。システムの性能や品質に関する要件で、ユーザーの満足度に直結します。
非機能要件はシステム開発の初期段階で明確に定義し、開発プロセス全体を通じて遵守することが必要です。非機能要件の定義が不十分な場合、システムが期待される品質を満たせず、プロジェクトの失敗につながる恐れがあります。
対策3:変更管理と優先順位付けでスコープクリープを防ぐ
前述の通り、スコープクリープはプロジェクトを崩壊させる大きな要因です。こうした問題を防ぐには、厳格な「変更管理プロセス」と、賢明な「優先順位付け」の徹底が重要です。
すべての要望に応えることが必ずしもプロジェクトの成功につながるわけではないことを理解し、戦略的にスコープをコントロールする必要があります。
対策4:先を見越したリスクマネジメントを行う
優秀なプロジェクトマネージャーは問題が起きてから対処するのではなく、問題が起きる前に先手を打ちます。要件定義の段階で、プロジェクトに潜む潜在的なリスクを洗い出し、事前に対策を講じます。
以下に、リスクマネジメントのプロセスをまとめました。
| リスク管理プロセス | 説明 |
|---|---|
| 1. リスクの特定 | プロジェクトに影響を与えうる不確実な事象を洗い出す。(例:主要メンバーの離脱、新技術の導入失敗) |
| 2. リスクの分析・評価 | 各リスクの「発生確率」と「影響度」を評価し、優先順位を付ける。 |
| 3. リスク対応計画の策定 | リスクへの対応策(回避、軽減、移転、受容)を計画する。 |
| 4. リスクの監視・コントロール | プロジェクトを通してリスクの状態を監視し、必要に応じて対応計画を見直す。 |
リスクは「リスク登録簿」と呼ばれる一覧表で管理して定期的にレビューすると、チーム全体の危機管理意識を高められます。
対策5:発注側と開発側の協働体制を築く
システム開発は、発注側と開発側のどちらか一方だけでは成功しません。両者が「ワンチーム」となり、各々の役割と責任を果たしながら、共通のゴールに向かって協力する体制を築くことが不可欠です。
発注側は業務知識を提供する専門家、開発側はITを実現する専門家として、お互いをリスペクトして対等なパートナーシップを築きましょう。
要件定義で役立つツールとフレームワーク

要件定義を効率的かつ効果的に進めるには、適切なツールやフレームワークの活用が欠かせません。本章では、前章までに紹介したものを含め、要件定義の各場面で役立つ代表的なものを一覧で紹介します。
| カテゴリ | ツール/フレームワーク名 | 主な用途 |
|---|---|---|
| コミュニケーション | Slack, Microsoft Teams | 日常的なチャット、情報共有、ファイル共有 |
| Zoom, Google Meet | オンライン会議、画面共有によるデモ | |
| 情報集約・書類作成 | Confluence, Notion | 議事録、仕様書、用語集など、プロジェクト情報の集約(Wiki) |
| Google Workspace, Microsoft 365 | 共同での書類編集、Googleスプレッドシート管理 | |
| モデリング・作図 | Miro, Lucidchart, Cacoo | 業務フロー図、マインドマップ、ワイヤーフレームなどの作図 |
| draw.io(diagrams.net) | 無料で利用できる高機能な作図ツール | |
| UI/UXデザイン | Figma, Adobe XD | 高忠実度なワイヤーフレーム、プロトタイプの作成 |
| タスク・プロジェクト管理 | Lychee Redmine, Backlog, Jira | タスク管理、課題管理、進捗の可視化 |
| フレームワーク | BPMN | 業務プロセスを標準化された記法で記述する |
| UML | システムの構造や振る舞いをモデリングするための標準言語 | |
| MoSCoW分析 | 要件の優先順位付けを行うためのフレームワーク | |
| RACIチャート | タスクごとの役割(実行責任者、説明責任者など)を明確化する |
要件定義の失敗事例から学びプロジェクト成功の礎を築こう

要件定義の失敗は、コミュニケーション不足やスコープ管理の不備、技術的検討不足など、複合的な要因で発生します。失敗を防ぐためには、認識の見える化や厳格な変更管理、リスクの先読みが不可欠です。
ツールやフレームワークを適切に活用すれば、要件定義の質と効率を大幅に向上させられます。重要なのは、発注側と開発側が「ワンチーム」となり、共通のゴールに向かって協力する協働体制を築くことです。
要件定義の失敗は、誰にでも起こり得ます。しかし、重要なのは失敗を恐れることではなく、過去の多くの失敗事例から学んで自身のプロジェクトに活かすことです。
30日無料トライアルをはじめる
- 多機能ガントチャート/カンバン/バックログ/リソース管理/CCPM/レポートなど
- ・ クレジットカード登録不要
- ・ 期間終了後も自動課金なし
- ・ 法人の方のみを対象
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。