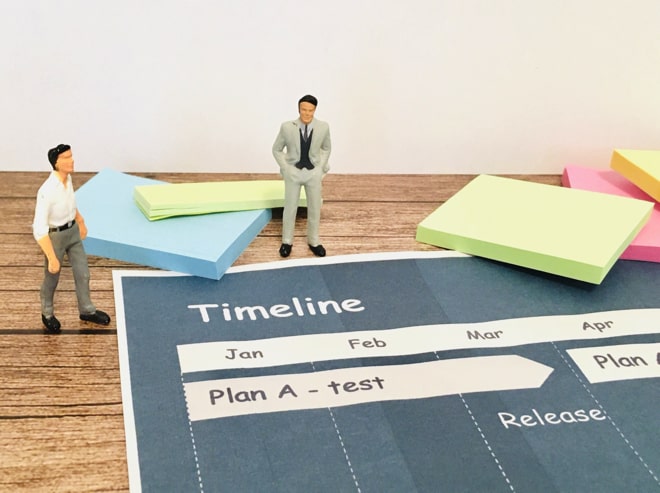「スコープマネジメント計画書には何を書けば良いのか」 「プロジェクトスコープ記述書との違いがわからない」といった疑問を持っている方は少なくありません。
本記事ではスコープマネジメント計画書とはどのようなものかを軸に、作成方法やプロジェクトスコープ記述書との違い、 よくある失敗例と対策、成功事例を解説します。ステップごとの具体的な手順や、すぐに使えるサンプルも用意しました。
本記事を参考に、より明確な目標設定や効率的なタスク管理、最終的なプロジェクトの成功を目指しましょう。
スコープマネジメント計画書とは

プロジェクトの内容や範囲をまとめ、実際の進行状況を確認しながら管理する際に使用される計画書です。プロジェクトの目的達成に向けて「何をやる必要があるか」「何をやらなくて良いのか」を明確に整理し、進むべき方向を定める上で重要な役割を持ちます。
また、関係するメンバー全員がスコープを正しく理解できるようになり、無駄な作業や範囲の不要な拡大を防ぐ効果もあります。
スコープマネジメント計画書が必要な理由
主な理由としては、以下の点が挙げられます。
| 理由 | 詳細 |
| プロジェクトの目標達成 | 目標達成に必要な作業に集中できるようになる |
| スコープクリープの防止 | 不要な作業の追加を防ぎ、プロジェクトの肥大化を抑制できる |
| 関係者との合意形成 | プロジェクトの範囲について関係者全員が共通認識を持つと、認識のずれによるトラブルを防げる |
| コストとスケジュールの管理 | より正確なコストとスケジュールの見積もりが可能になり、遅延や予算超過を防げる |
もしも計画書がない場合、方向性が曖昧になり、関係者の間で認識のずれが生じやすくなります。結果として遅延や予算超過、品質低下などの問題が発生する可能性が高まります。
したがって、プロジェクトを成功させるには必要不可欠と言えます。
スコープマネジメント計画書作成のタイミング
なるべく早い段階で作成するのが重要です。
具体的には、プロジェクトを始める準備段階や計画を立て始めた時点で作成するのが理想的です。全体的な方向性を明確にでき、その後の作業の指針として役立ちます。
具体的には、以下のようなタイミングが適しています。
| タイミング | 詳細 |
| プロジェクト憲章の作成後 | プロジェクトの目的や概要が決まったタイミングで、計画書の作成を始める |
| ステークホルダーの特定後 | 誰がプロジェクトに関わるのかを明確にし、各関係者の要望を集める前に、計画書の作成に着手する |
| 要求事項収集の準備段階 | 具体的な要望を収集する前に、プロジェクトの範囲をいかに定義・記録し、確認するかを計画書にまとめておく |
早い段階で計画書を整備すると、チーム内での共通認識が生まれ、一貫性のある活動が行えます。結果、後からの修正や作業のやり直しを大幅に減らす効果も期待できます。
スコープマネジメントの方法

計画書を作成する上で、スコープマネジメントの方法の把握は不可欠です。本章では、基本的な方法を6つのステップに分けて解説します。
ステップ1:スコープ計画を立てる
スコープをいかに定義、管理、検証、コントロールするか計画します。結果として、関係者全員が共通認識を持てます。
スコープ計画を立てる際には、主に以下の要素を考慮しましょう。
- プロジェクトの目標:何を達成したいのかを明確にする
- 成果物:プロジェクトが完了した際に何が提供されるのかを定義する
- タスク:成果物を完成させるために必要な作業を洗い出す
- 役割と責任:誰がどのタスクを担当するのかを明確にする
- スケジュール:各タスクの開始日と終了日を設定する
- 予算:各タスクに割り当てる予算を決定する
- リスク:スコープに影響を与える可能性のあるリスクを特定する
ステップ2:要求事項を収集する
次に、関係者(顧客、ユーザー、チームメンバーなど)から、プロジェクトに対する要求事項を収集します。要求事項を収集すると、スコープをより具体的に定義できます。
要求事項を収集する方法としては、以下のようなものがあります。
- インタビュー:関係者に直接話を聞き、要求事項を詳しく把握する
- アンケート:多くの関係者から効率的に要求事項を収集する
- ワークショップ:ブレインストーミングやディスカッションで要求事項を洗い出す
- 書類分析:既存の書類(仕様書、契約書など)を分析する
ステップ3:スコープを定義する
収集した要求事項に基づいて、スコープを定義します。プロジェクトの範囲が明確になり、不要な作業や機能の追加を防げます。
スコープを定義する際には、主に以下の要素を記述します。
- 受け入れ基準:成果物が満たすべき品質基準を記述する
- 除外事項:スコープに含まれないものを記述する
- 制約事項:スコープに影響を与える制約事項(予算、スケジュールなど)を記述する
ステップ4:WBSを作成する
WBS(Work Breakdown Structure)とは、プロジェクトの成果物と作業を、より小さく管理しやすい要素に分解したものです。スコープをより詳細に把握し、タスクの割り当てや進捗管理を容易にできます。
WBSを作成する際には、以下の点に注意しましょう。
- 成果物中心:タスクではなく、成果物を中心に構成する
- 階層構造:最上位の成果物から、より細かいタスクへと階層的に分解する
- MECE(ミーシー):漏れなく、重複なく、すべてのタスクを網羅する
ステップ5:スコープの妥当性を検証する
作成したスコープが、プロジェクトの目標や要求事項を満たしているか検証します。結果として、方向性を確認し、手戻りを防げます。
スコープの妥当性を検証する方法としては、以下のようなものがあります。
- レビュー会議:関係者を集めてスコープの内容をレビューし、意見交換を行う
- プロトタイプ作成:一部をプロトタイプとして作成し、関係者に評価してもらう
- テスト:スコープに基づいてテストケースを作成し、テストを実施する
ステップ6:スコープの管理・調整を行う
進行途中で、予期せぬ変更や問題が発生する可能性があります。そのため、スコープを継続的に管理し、必要に応じて調整を行いましょう。
結果として、スコープクリープを防げて、計画通りに進められる可能性が高まります。
スコープを管理・調整する際には、以下の点に注意しましょう。
- 変更管理プロセス:スコープの変更を管理するためのプロセスを確立する
- 影響評価:スコープの変更がスケジュール、予算、品質に与える影響を評価する
- 承認:スコープの変更を承認する権限を持つ人を明確にする
- コミュニケーション:スコープの変更について、関係者全員に周知する
上記のステップを実践すると、効果的に管理でき、成功へとつなげられます。
スコープマネジメント計画書のサンプル

以下は、一般的な計画書のサンプル構成です。プロジェクトの特性に合わせて、必要な項目を追加・修正してください。
| 項目 | 説明 | 記載例 |
| 1. プロジェクト概要 | 目的、目標、背景などを簡潔に記述 | 新製品開発プロジェクト:市場ニーズに応える革新的な〇〇を開発し、市場シェア10%を獲得する |
| 2. スコープ概要 | プロジェクトで提供する成果物、サービス、結果を明確に定義 | 成果物:製品〇〇のプロトタイプ、製品仕様書、テスト結果報告書 |
| 3. プロジェクトの制約 | プロジェクトの遂行を制限する要因を記述 | 予算:1,000万円 納期:2024年12月末 リソース:開発チーム5名 |
| 4. プロジェクトの前提条件 | プロジェクトの遂行を前提とする条件を記述 | 前提条件:必要な技術は開発チームが習得済みであること、必要なデータは外部機関から提供されること |
| 5. スコープ定義の方法 | スコープの定義に使用するプロセス、ツール、技法を記述 | 要求収集:顧客へのインタビュー、アンケート調査、競合製品の分析 スコープ定義:WBS(Work Breakdown Structure)の作成、ステークホルダーレビュー |
| 6. WBS | 成果物をより小さく、管理しやすいタスクに分解した階層構造図 | 後述 |
| 7. スコープ検証の方法 | スコープの妥当性を検証するプロセスを記述 | 成果物レビュー:各タスク完了後に、関係者によるレビューを実施 顧客による受入テスト:最終成果物に対して、顧客による受入テストを実施 |
| 8. スコープ管理の方法 | スコープの変更を管理するプロセスを記述 | 変更要求受付:スコープ変更要求は、プロジェクトマネージャーが受け付ける 影響分析:変更要求の影響範囲(コスト、スケジュール、品質など)を分析する 変更承認:ステークホルダー会議で変更要求を承認するかどうかを決定する |
以下は、新製品開発プロジェクトにおけるWBSのサンプルです。
| レベル1:プロジェクト | レベル2:成果物 | レベル3:タスク |
| 新製品開発プロジェクト | 1. 製品設計 | 1.1 要件定義 1.2 基本設計 1.3 詳細設計 |
| 2. プロトタイプ開発 | 2.1 部品調達 2.2 プロトタイプ組み立て 2.3 動作テスト | |
| 3. テスト | 3.1 機能テスト 3.2 性能テスト 3.3 ユーザビリティテスト |
上記のサンプルはあくまでも一例です。実際のプロジェクトでは、より詳細な計画書およびWBSを作成する必要があります。
プロジェクトスコープ記述書との違い

スコープマネジメント計画書と混同しやすいものとして、プロジェクトスコープ記述書があります。どちらもプロジェクトの範囲を定めるものですが、役割と内容には明確な違いがあります。本章では、各書類の役割と重要性、両者の関係性について解説します。
プロジェクトスコープ記述書の役割と重要性
プロジェクトスコープ記述書は、成果物、作業範囲、前提条件、制約条件などを詳細に記述した書類です。目的を達成する上で「何をすべきか」「何をしないか」を明確にし、関係者間で共通認識を持つ目的で作成されます。
主な役割は以下にまとめました。
- 範囲を明確化し、関係者間の認識のずれを防ぐ
- 目標、成果物、前提条件、制約条件を定義する
- 成功基準を定める
- 進捗状況を評価する基準を示す
プロジェクトスコープ記述書はプロジェクトの初期段階で作成され、プロジェクト全体を通して参照されます。結果として、メンバーは常にプロジェクトの目標と範囲を意識し、無駄な作業やスコープクリープを防げます。
したがって、プロジェクトスコープ記述書の作成はプロジェクトにおいて非常に重要です。
計画書と記述書の関係性
スコープマネジメント計画書とは、スコープをいかに定義して管理していくのか、方法や手順をまとめた文書です。具体的には、「プロジェクトスコープ記述書」を作成し、いかに管理・更新するかを決めておきます。
一方で、プロジェクトスコープ記述書は、プロジェクトで実施する作業の内容や範囲そのものを詳しく定めた文書です。
つまり、スコープマネジメント計画書は「スコープの管理方法」を示したものであり、プロジェクトスコープ記述書は「スコープそのものの内容」を示したものである点に違いがあります。
スコープマネジメントのよくある失敗と対策

スコープマネジメントはプロジェクトの成功に不可欠ですが、実際には様々な失敗が起こり得ます。本章では、よくある失敗例と対策について解説します。
失敗例1:要求事項の定義不足
プロジェクト開始時に、要求事項が十分に定義されていないと、後々になって必要な機能や、満たしていない条件が発覚するといった問題が発生するリスクがあります。
要求事項の定義不足は、手戻りや追加コスト、納期遅延の原因です。さらに、ステークホルダー間の期待値のずれを生み、プロジェクト全体のモチベーション低下にもつながります。
要求事項の定義不足による失敗を避けるには、以下の対策を講じましょう。
- 関係者と綿密にコミュニケーションを取り、要求事項を詳細に聞き出す
- 要求事項定義書を作成し、関係者全員で合意形成を行う
- 要求の具体像を可視化し、認識のずれを早期に発見する
失敗例2:スコープクリープ(スコープの拡大)
スコープクリープは、プロジェクトの進行中に、当初の計画にはなかった要求や機能が追加され、プロジェクトの範囲が徐々に拡大していく現象です。プロジェクトの目標が曖昧な場合や、変更管理が適切に行われていない場合に発生する可能性があります。
スコープクリープが発生すると、プロジェクトのスケジュールが遅延したり、予算が超過したりするリスクが高まります。また、メンバーの負担が増加し、品質低下にもつながる可能性があります。
スコープクリープの発生を防ぐには、以下のような対策を講じましょう。
- 明確なスコープ定義を行い、プロジェクトの範囲を明確化する
- 変更管理プロセスを確立しつつ、要求変更時は影響を評価して承認を得る
- ステークホルダーとの密なコミュニケーションで、スコープ変更に関する合意形成を行う
失敗例3:コミュニケーション不足
プロジェクトメンバー間やステークホルダーとのコミュニケーション不足は、スコープマネジメントの失敗につながります。情報共有が不十分だと、認識のずれが生じ、手戻りや誤解が発生する可能性があります。
特にリモートワーク環境では、意図的なコミュニケーションを心がける必要があります。
コミュニケーション不足を解消するには、以下のような対策を講じましょう。
- 定期的な会議や報告会を開催し、情報共有を徹底する
- コミュニケーション計画を作成し、情報伝達のルールや方法を明確化する
- コミュニケーションツール(チャット、グループウェアなど)を活用し、円滑な情報共有を促進する
失敗例4:要件変更管理プロセスの欠如
プロジェクト途中での要件変更は避けられない場合もあります。しかし、要件変更の管理プロセスが確立されていないと、変更が適切に評価・管理されず、プロジェクトに悪影響を及ぼす可能性があります。
要件変更管理プロセスの欠如を避けるには、以下のような対策を講じましょう。
- 要件変更申請の手順を明確化し、変更の影響を評価する
- 変更管理委員会を設置し、変更の承認を行う
- 変更履歴を記録し、変更内容を追跡できるようにする
スコープマネジメントを活用したプロジェクト成功事例

本章では、コスト削減、納期遵守、顧客満足度向上といった観点から3つの成功事例を紹介します。
事例1:コスト削減に成功したプロジェクト
ある製造業の会社では、新製品開発プロジェクトの初期段階におけるスコープ定義が曖昧だったために開発途中で機能追加が頻繁に発生し、予算超過が深刻化していました。
プロジェクトマネージャーは、スコープマネジメント計画書を見直し、要求事項の収集とスコープ定義を徹底的に行いました。
顧客へのヒアリングを重ね、必要な機能と不要な機能を明確に区別し、スコープから外れる機能を明確に除外しました。また、変更管理プロセスを導入し、スコープ変更が発生した場合は影響範囲とコストを評価し、承認を得るプロセスを確立しました。
結果として、スコープクリープを抑制し、不要な機能開発の削減に成功しました。最終的に、プロジェクトは当初予算内で完了し、コスト削減に大きく貢献しています。
事例2:納期遵守を達成したプロジェクト
あるソフトウェア開発会社では、大規模なシステム開発プロジェクトで、過去に納期遅延が頻発していました。原因を分析した結果、プロジェクト初期段階でのスコープ定義の甘さが、手戻りの増加やタスクの遅延を招いている事実が判明しました。
上記の問題を受け、次のプロジェクトでは、スコープマネジメント計画書を詳細に作成し、WBSを用いてタスクを細分化し、各タスクの担当者と期日を明確にしました。さらに、定期的な進捗会議を実施し、スコープの逸脱や遅延が発生していないかをモニタリングしました。
遅延が発生した場合には、迅速に原因を特定して是正措置を講じ、納期遅延を最小限に抑制できました。結果として、プロジェクトは当初予定されていた納期を遵守し、顧客からの信頼獲得につながっています。
事例3:顧客満足度向上を実現したプロジェクト
あるマーケティング会社では、Webサイトリニューアルプロジェクトを、顧客の要望を十分に把握しないまま進めました。結果的に、納品後に顧客からの修正依頼が相次ぎ、顧客満足度が低下していました。
上記の問題を受け、次のプロジェクトでは、スコープマネジメント計画書を作成する際に顧客とのコミュニケーションを重視し、要求事項の収集に注力しました。
具体的には、複数回のヒアリングを実施し、顧客のニーズや期待を詳細に把握しました。また、要件定義書を作成して顧客にレビューしてもらい、認識の齟齬を解消しました。
さらに、プロジェクトの進捗状況を定期的に顧客に報告し、フィードバックを求めて、顧客の期待に応えるWebサイトの開発に成功しています。結果として、顧客満足度は大幅に向上し、リピート率の向上にもつながりました。
スコープマネジメント計画書でプロジェクトを成功に導こう

スコープマネジメント計画書は、プロジェクトの目標達成に向けて、関係者全員が共通認識を持ち、効果的な管理・調整を行う上で非常に重要です。
効果的に運用するには、プロジェクトの初期段階で綿密なスコープ計画を立て、要求事項を丁寧に収集し、明確なスコープを定義する必要があります。WBSを作成しつつ、スコープの妥当性の継続的な検証も、プロジェクトを成功に導く上で重要なステップです。
本記事で紹介した成功事例も参考に、スコープマネジメント計画書を最大限に活用し、プロジェクトの成功へとつなげましょう。
30日無料トライアルをはじめる
- 多機能ガントチャート/カンバン/バックログ/リソース管理/CCPM/レポートなど
- ・ クレジットカード登録不要
- ・ 期間終了後も自動課金なし
- ・ 法人の方のみを対象
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。