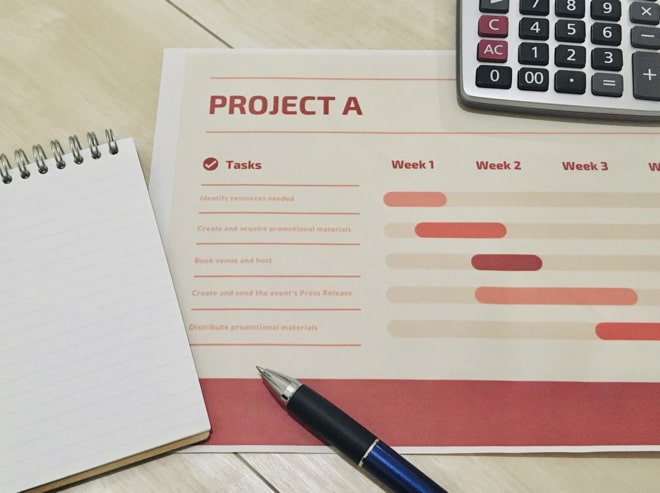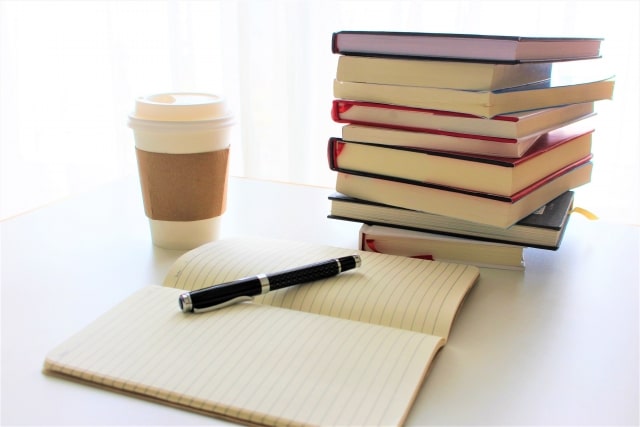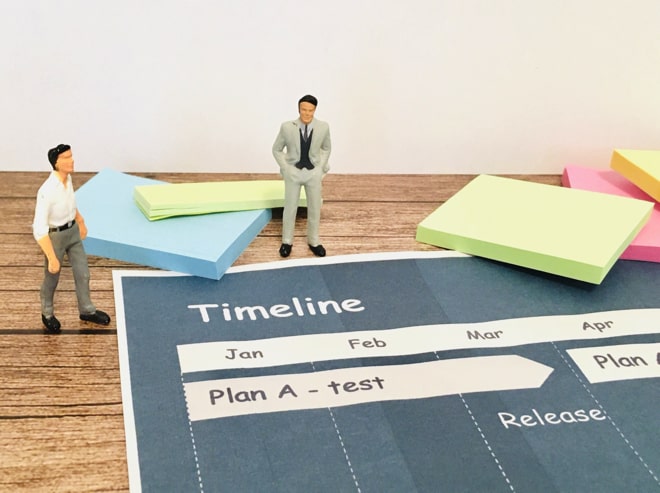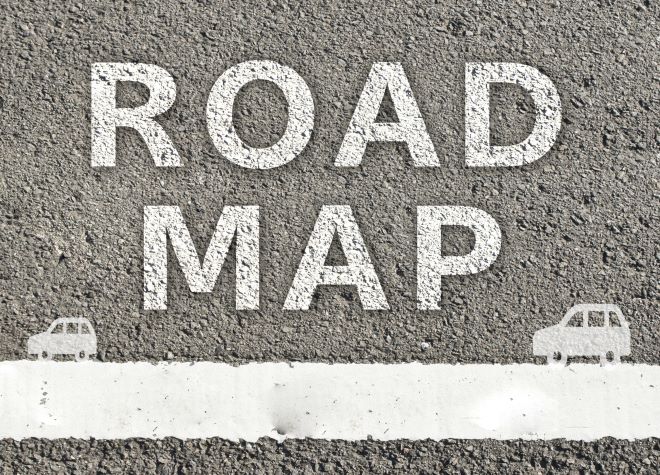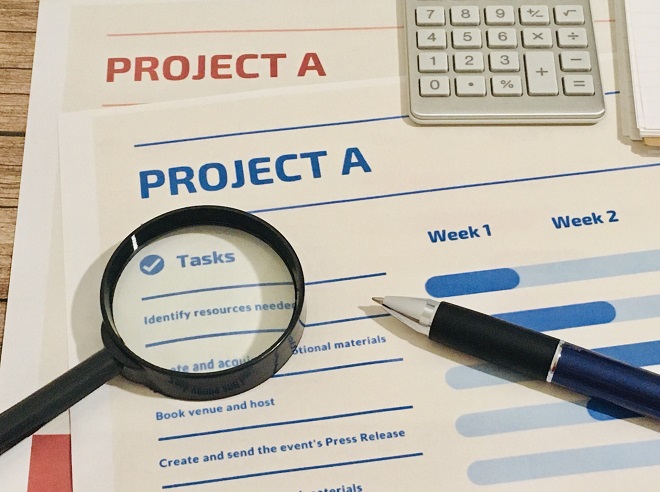「プロジェクト計画を作れと指示されたが、なぜプロジェクト計画を作るのかわからない」
「そもそもプロジェクト計画をどのように作ったらいいのかわからない」
プロジェクトを始めるにあたり、このような疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
プロジェクト計画は、プロジェクトの成功に必要不可欠な存在です。
とはいえ、混乱や手戻りの少ないプロジェクト計画を作るのは、ベテランでも難しいもの。
今回の記事では、プロジェクト計画の概要や作成手順、実際のプロジェクト計画書に記載すべき項目について解説します。
プロジェクト計画とは
 プロジェクト計画とは、プロジェクトを成功させるために必要な要素を網羅したものです。
プロジェクト計画とは、プロジェクトを成功させるために必要な要素を網羅したものです。
プロジェクト計画を作成する際は、以下の要素を検討し、記載する必要があります。
- プロジェクトのゴールと目的
- 対象物の範囲、成果物(スコープ)
- コスト
- スケジュール
- プロジェクト体制
- 品質
- コミュニケーションルール
- リスクと対応
プロジェクト計画が必要な理由
プロジェクト計画は、プロジェクトの成功確率を上げるために必要です。
プロジェクトは大きくなるほど多くの人が参加します。
しかし、明確でわかりやすいプロジェクト計画がないと、それぞれの認識に齟齬が生じやすくなります。
小さな齟齬が重なると、当初の目的やゴールからずれやすくなるため、プロジェクトが失敗してしまうことも。
プロジェクト計画を作っておけば、認識の齟齬が生じにくくなり、当初の目的やゴールから大きくずれてしまう事態を防げます。
プロジェクト憲章、作業計画、プロジェクトスコープとの違い
プロジェクト計画と似た言葉として、プロジェクト憲章、作業計画、プロジェクトスコープがあります。
それぞれの違いと一致している点を確認し、混同しないように理解しておきましょう。
プロジェクト計画とプロジェクト憲章の違い
プロジェクト憲章とは、プロジェクト計画を立てる前に明確にすべき、プロジェクトの企画書ともいえるものです。
プロジェクト憲章には次にあげる3点が含まれている必要があります。
- 「なぜ」プロジェクトを行うのか
- 「何」をプロジェクトで行うのか
- 「誰」がプロジェクトを行うのか
上記の内容を明確にし、ステークホルダーに合意を得ることで、はじめてプロジェクトはスタートします。
プロジェクト計画と作業計画の違い
プロジェクト計画と作業計画は、名称は異なるものの内容はほとんど同じです。
チームや会社によって呼び名は異なりますが、どちらもプロジェクト達成に必要なステップが記されています。
プロジェクト計画とプロジェクトスコープの違い
プロジェクトスコープは「誰が、何を、どこまでやるか」といった「範囲」を定義するもので、プロジェクト計画に含まれています。
プロジェクトスコープはプロジェクト計画の初期段階で作成し、その後に洗い出すすべてのステップの基礎となるものです。
非常に重要なステップのため、規模が大きいプロジェクトでは別途「スコープ定義書」を作成する場合もあります。
プロジェクト計画の作成に必要な5ステップ
 プロジェクト計画には、以下の5ステップが必要です。
プロジェクト計画には、以下の5ステップが必要です。
- プロジェクトスコープの定義
- 人的リソースの見積もり
- スケジュールの決定
- コストの見積もり
- リスクアセスメントの実施
計画段階では、上記の順で検討していく必要があります。
何を、誰が、いつまでに、いくらくらいの予算で、と進めていくと検討内容に手戻りが生じにくく、効率よくプロジェクト計画が策定できるためです。
1. プロジェクトスコープを定義する
まずすべきは、プロジェクトスコープの定義です。
プロジェクトスコープを定義するためには、以下の2ステップで進めましょう。
ステップ1:ゴールと目的の明確化
まず、ゴールと目的を明確にします。
何をなすべきか、目的や目標は何か、制約となる条件はあるか、などについて検討しましょう。
ステップ2:必要な作業の洗い出し
続いて、目的の達成に必要なすべての作業を洗い出します。
洗い出す際は、なるべく粒度の大きいタスクから洗い出し、徐々にタスクを分解して粒度の小さいタスクにしていきましょう。
このように構造化・リスト化して洗い出していくと、作業の重複や漏れを防げます。
2. 人的リソースを見積もる
やるべきことが明確になったら、人的リソースの見積もりに移ります。
どの作業を誰に割り当てるか、どの部分を外注や調達でまかなうかも含め、必要な人的リソースを割り出しましょう。
組織図や役割表の形式で記載すると、わかりやすくなります。
| 名称 | メリット | デメリット |
| 組織図 | 視覚的にプロジェクト体制が確認しやすい | 個々の役割がわかりにくい |
| 役割表 | 個々の役割がわかりやすい | 体制がわかりにくい |
組織図と役割表は、両方作るのがベストです。
3. スケジュールを決める
作業の順序や必要な期間から、全体のスケジュールを策定します。
以下のような項目を検討し、マスタスケジュールから詳細なスケジュールへと細部を詰めていきます。
- 全体工期
- 着手時期
- マイルストーン
- ローンチ日
4. コストを見積もる
人件費や場所、ツールなどの費用は、スケジュールに大きく依存します。
そのため、必要な作業量と作業期間を見積もってからコストを見積もりましょう。
収支を計画し、実行予算を見積もります。
5. リスクアセスメントをする
プロジェクト計画に必要な要素が洗い出されたら、最後にリスクアセスメントをします。
予想されるすべてのリスクを洗い出し、対策を決定します。
リスクが大きい場合は、計画の見直しと修正も必要となるかもしれません。
プロジェクト開始後に思わぬトラブルが起こらないよう、計画段階ですべてのリスクを洗い出すように意識しましょう。
プロジェクト計画書に記載すべき項目8つ
 プロジェクト計画をステップに沿って作成していけば、自然に計画書に記載する内容も定まってきます。
プロジェクト計画をステップに沿って作成していけば、自然に計画書に記載する内容も定まってきます。
プロジェクト計画書に記載すべきは、以下の8項目です。
1. プロジェクトの概要
プロジェクトの概要には、目的とゴールについて記載します。
認識の食い違いを防ぐためにも、わかりやすく簡潔に記載するのが大切です。
目的
目的の欄では、「何のためのプロジェクトか」を簡潔に書きます。
役員に見せる場合は、企業戦略との結びつきも記載できるとなおよいでしょう。
ゴール
ゴールを記載する際は、QCD(品質、費用、期限)を明確にして記載しましょう。
| Q(品質) |
成果物の品質、運用品質など |
| C(費用) | 原価率、利益目標 |
| D(期限) | マイルストーンとローンチ日を設定それぞれのゴールはできる限り数値化しておくと、達成したかどうかがわかりやすくなります。 |
2. 作業の範囲、成果物(スコープ)
続いて、どのような作業をどこまでするのか、成果物は何か、といったスコープを記載します。
スコープ定義の段階で作業を洗い出していくと、WBS(Work Breakdown Structure:作業分解構成図)ができあがります。
作業の範囲はWBSからの抜粋でかまいませんが、WBS自体がスケジュールの素案となるため、プロジェクト計画書に資料として添付しておきましょう。
成果物とは、プロジェクトの区切りごとに期待されるアウトプットをさします。
成果物を定義する場合は、マイルストーンとからめて定義すると、進捗管理が可視化されて便利です。
3. コスト
コストのスライドは、内部向けの計画書にのみ記載します。
プロジェクト計画書に記載する場合は、下記くらいの比較的ざっくりとしたレベルで記載すれば問題ありません。
- 人件費
- 外注費
- ソフトウェア費用
- ハードウェア費用
- インフラ費用
- 保守費用
- ライセンス費用
- 備品費
見積もりレベルの細かい費用については、添付資料にしましょう。
4. スケジュール
スケジュールのスライドには、全体を要約したマスタスケジュールを記載します。
マスタスケジュールに記載すべきは、以下のような項目です。
- マイルストーン
- クリティカルパス
- 管理指標
WBSが詳細なスケジュールとして機能するため、あまり細かいスケジュールを記載する必要はありません。
5. プロジェクト体制
プロジェクト体制では、以下の事項を必ず明記します。
- 社内外含めたプロジェクトの全登場人物
- 各要員の役割
- 責任者の所在
プロジェクト体制は、組織図と役割表の2パターンで書くと理解しやすくなります。
6. 品質
品質のスライドでは、プロジェクトで達成すべき品質基準を明確に記載しましょう。
| 項目 | 目標値 | 期間 | 管理方法 |
| 稼働率 バグ発生数など |
99%以上 月に3回未満など |
1ヶ月 1週間など |
24時間体制の管理 テストの実施など |
品質に関する記載事項は、ボリュームが大きくなりがちです。
品質のスライドが長くなりそうな場合は、品質定義書を別途用意しましょう。
7. コミュニケーションルール
コミュニケーションがうまくいくかどうかは、プロジェクトの成否に大きく影響します。
ですが、当然できると考えられがちで、意外に盲点になりがちなポイントです。
どのようにコミュニケーションをとるか、中間報告をどのようにするかをルール化しておきましょう。
具体的には、以下の項目を決めます。
会議の開催ルール
- 名称
- 出席メンバー
- 目的
- 開催頻度、時間
コミュニケーションのルール
- メールのルール(TOやCCの利用方法、件名の設定方法など)
- プロジェクトを管理するツール名と運用ルール
- 議事録の作成ルール(作成者、通知方法など)
コミュニケーションのルールを作成したら、全参加者に周知しておきましょう。
8. リスクと対応
考えうるすべてのリスクを洗い出し、リスクに対する対応策を明確にします。
リスクについては、下記の項目をあらかじめ検討しておきましょう。
- リスク内容
- 発生確率
- 発生頻度
- 重要度
- 対応策
リスクに対する備えがあるかどうかで、プロジェクト計画の成否が大きく左右されます。
事前にある程度検討しておくと、スケジュールやコストのずれを防げます。
プロジェクト計画を作成する際の注意点2つ
 プロジェクト計画は、作成した後に修正したり、担当者が変わったりする可能性があります。
プロジェクト計画は、作成した後に修正したり、担当者が変わったりする可能性があります。
修正や変更があっても混乱しないために、下記の2点に注意して作成しましょう。
1. フォーマットを決めておく
プロジェクト計画を作成する際に意識しておきたいのが、フォーマットを決めておくことです。
プロジェクトは、計画段階でも、プロジェクト開始後であっても、修正が起こる可能性があります。
その際に決められたフォーマットがないと、修正作業に大きな手間と時間がかかってしまいます。
また、プロジェクト計画を修正するのが作成者と違う場合もあるかもしれません。
その場合も、フォーマットが決まっていないと混乱や認識の食い違いが起こる可能性が出てきます。
こうした混乱を防ぐためにも、あらかじめフォーマットを決めて情報を共有しておきましょう。
2. 情報共有を徹底する
プロジェクト計画書に多くの人が関わるほど、情報共有が重要になります。
内容の周知はもちろんのこと、プロジェクト計画書の記載方法や読み方などについても情報共有しておきましょう。
情報共有を徹底することで、認識の食い違いが生じるのを防ぎ、修正や手戻りのコストが発生するのを防げます。
プロジェクト管理ツール「Lychee Redmine」の紹介

プロジェクト計画に役立つツールとして、7,000社以上の導入実績を持つLychee Redmineをご紹介します。
Lychee Redmineはガントチャートやカンバンなど、プロジェクト管理に必要な機能が豊富に搭載されているにもかかわらず、直感的な操作で誰でも簡単に使えるのが特徴です。
また、バックログやタイムマネジメント、コスト管理などさまざまな視点で管理・確認できる機能も備わっているので、うまく活用すればプロジェクト計画作成にも役立つでしょう。
Lychee Redmineは有料プランであっても30日間無料で試すことが可能です。無料期間終了後も自動課金しないため、安心して利用いただけます。
プロジェクト計画の作成に課題を感じている方や、より精度の高いプロジェクト計画を作成したい方はこの機会にぜひ一度お試しください。
プロジェクト管理ツール「Lychee Redmine」を使ってみる。(30日間無料・自動課金なし)
| プラン | 月額料金 | 利用機能 |
| フリー | 無料 |
|
| スタンダード | 900円 |
|
| プレミアム | 1,400円 |
|
| ビジネス[無料トライアルはこちらをお試しできます] | 2,100円 |
|
ポイントをおさえたプロジェクト計画を作成しよう
 プロジェクト計画の概要と作成手順、計画書に記載すべき項目について紹介しました。
プロジェクト計画の概要と作成手順、計画書に記載すべき項目について紹介しました。
プロジェクト計画で検討すべきは以下の8つです。
- プロジェクトのゴールと目的
- 対象物の範囲、成果物(スコープ)
- コスト
- スケジュール
- プロジェクト体制
- 品質
- コミュニケーションルール
- リスクと対応
プロジェクト計画は、関係者の認識をすり合わせるために重要です。
混乱や認識の齟齬が起きないよう、フォーマットを決めておき、情報共有を徹底する点も意識しておきましょう。
30日無料トライアルをはじめる
- 多機能ガントチャート/カンバン/バックログ/リソース管理/CCPM/レポートなど
- ・ クレジットカード登録不要
- ・ 期間終了後も自動課金なし
- ・ 法人の方のみを対象
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。